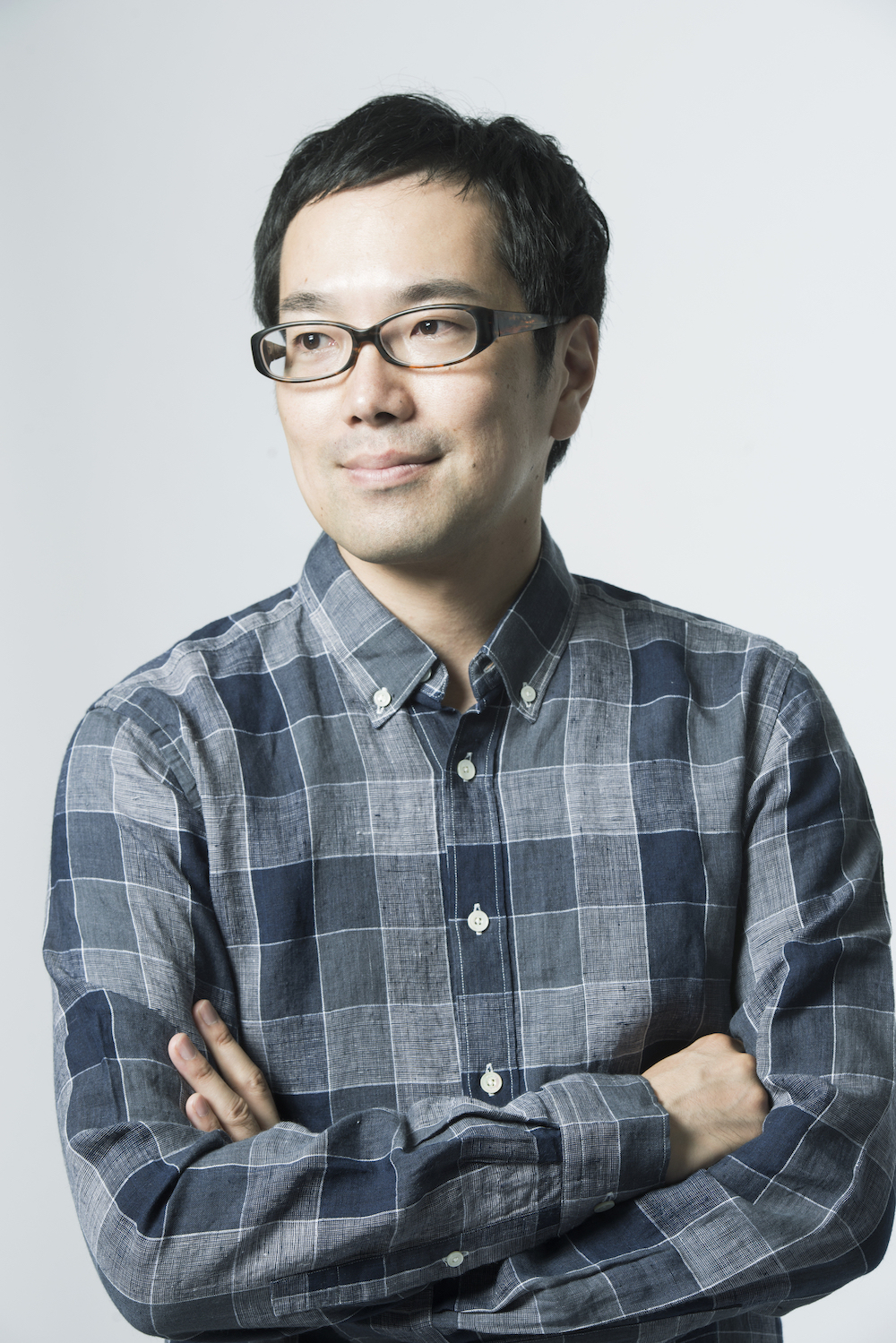「伝える」とはなんなのか?
山本浩貴(以下、山本):スペースノットブランクの作品はこれまでかなりの数が発表されてきているけれど、ひどく大まかに分けるなら3つほどの方向性が挙げられると思う。すなわち、①(肉体の運動を見せることを重視した)ダンス的方向性、②(物語性のある戯曲を自分らで用意したり、あるいは外部の書き手によるそれを採用したりすることで実現する)演劇的方向性、③(観客とのあいだで生じる関係性を実験的に操作していく)インスタレーション的方向性。これらがそれぞれの作品で、いずれかに比重を置いたり、絡まり合ったりしつつ展開されていくところがある。
今回、hさんとふたりで「プレビュー上演」を見た『本人たち』は、この3つのうち③の傾向の強い作品のひとつだと思う。軽く背景に触れておけば、第一部「共有するビヘイビア」は2018年と2019年に会話とダンスから成る作品として発表され、さらに2021年に『クローズド・サークル』という会話と映像操作中心の作品へと発展させられたのち、今回に至る。第二部「また会いましょう」は2022年に展示作品として発表されたのち、今回に至る。そして総体としては、2020年にスペノがコロナ禍を受けて始めたプロジェクト『本人たち』の延長線上にあるものとして組み上げられているとされる。
その上で、今回の『本人たち』は、まだ本番がどうなるかわからないけれど、少なくともプレビュー上演だけで言えば、③インスタレーション的方向性として作られたスペノ作品のなかでも特に方法論が明確で、完成度の高いものになりつつあるように感じられた。作品の制作過程で収録された会話や私的発話を記録、編集し、戯曲化して舞台上の肉体に発話させるやり方も、これまで以上に発展・洗練されていたし──どうでもいいような細部の話や身振りがほとんどすべてゆるやかに必然的な意味を持つような構成が取られていたし──、発話方法や「念力暗転」という技(舞台上の肉体が観客に向けて瞼をゆっくり閉じるように促していく、結果、照明などが点いたまま舞台が暗転する)に代表されるような、観客との関係性の設計と操作に関しても、ことごとくクリティカルなものとして響くように仕組まれていたと思う。
なによりそれらのもたらす完成度の高さをめぐる認識が、作品の描く情動や主題や物語の厚みといったかたちをとらず、徹底して、作品全体を通じて提示されるところの方法論の明確さと強さ、そのシンプルさに由来しているようであることに、驚かされるところがあった。なかなか伝わりづらい言い方になっちゃうけれど、この作品のなかで語られる内容も、形式も、ひとつひとつはぺらぺらなまま、それでいていずれもが喩的な意味合いを託されるようにうまく構成されていて、結果としてあらゆる雑多な部分がたったひとつのシンプルな問い──「上演とは何か」──に十全に寄与し検証するものとなっている。その演出・構成の精緻さにおののくというようなところがあった、という感じかな。
hさんは今回、スペノの作品は初めて見たと思うけれど、どうだった?
h:「伝える」ってなんだろう、と思って見てた。第一部の古賀友樹さんの演技に特徴的だけれど、ものすごく観客の側を巻き込んで、いろいろなことを伝えてくる。台詞のなかでも──プレビュー上演時点で使っていた戯曲のデータをもらったからそこから引用すると──《何を伝えようかなって考えてる顔でした》《現在の状況についてお伝えさせてください》とか、「念力暗転」の実演のときに《この素晴らしい発明をした人物から「私」はその技を伝授され 今「あなた」に伝えています》って言うとか、いろんな箇所で「伝える」ことについて直接的に言及していた。
あと、これまで発表されてきた「共有するビヘイビア」を振り返るみたいなところでも、はっきり言われてたよね。《根底に共通するのは何かを伝えるということ しかもそれは矢印としては伝えるというベクトルが向いているということが全てで共通していると思います ダンスの工程とか なぜこのダンスが生まれたか 紹介する 説明とか 紹介っていうのがこの共有するbehaviorを説明する上で正しい伝え方だと思っていて 今説明の説明をしてる だから何者であるとかとか どういう存在であるかとかはある種関係なくて この現象を伝えようとしている「私」とそれを聞こうとしてくれている「あなた」このダンスを伝えます このダンスの背景を伝えます みたいな》って。ここは山本くんがいま言っていた、ひとつひとつの要素はぺらぺらなまま単一のシンプルな問いに収斂していく、という話に自己言及的にふれているところでもある。
山本:そうそう。《何者であるとかとか どういう存在であるかとかはある種関係なくて この現象を伝えようとしている「私」とそれを聞こうとしてくれている「あなた」》が重要なんだ、ってね。話される個々の話題やその主体の個人的情報に重きが置かれるのではなく、それらが立ち上げうるところの「伝える」関係性こそが問題なんだ、と。
h:ただ、その上で、この作品が「伝える」ことを絶望的なものとして捉えているのか、それとも希望として捉えているのか、まだちょっとわかってない。そこが気になる。
古賀さんのあの、ディズニーランドのキャストみたいな喋り方って、なんなんだろう。すごい語りかけてくるんだよね。最初から最後まで。
山本:本編はもちろん、開場後、上演の始まる前の時間にも、古賀さんがひとり舞台の上で観客に向けてめちゃくちゃ喋りかけてくる(笑)。そしてそのまま殆どシームレスに上演が始まり、第一部が終わったあと、第二部までの休憩時間にも延々と話している。
h:終わったあと質問すればよかったけれど、古賀さんはプレビュー上演のときのあの格好のまま、本番もやるのかな。
山本:すごいラフな格好だったよね。制作スタッフみたいというか。
h:喋り方も丁寧な感じで、いわゆる演劇上演前の事務連絡について話したりもする。もちろん俳優に前説を喋らせる演出ってよくあると思うんだけれど、それとも一線を画していた気がする。眼の前の俳優が観客である自分たちに語りかけてきているのか、それとも舞台上で完結しているのか、本当にわからなくなるというか……あなたは私に伝えたいの? それとも自分が練習してきたことをここでやりたいの? っていう、そこの境目がなくなる感じ。
山本:「あなた」って、古賀さんのこと?
h:そう。演劇って、もちろん観客に何かを伝えたくて上演するということもあると思うんだけれど、別にそのときも、観客を直接的に巻き込む必要は実はない。そこで完結しててもいいというか。俳優が観客に語りかけたりすることがあったとしても、実際には、俳優や劇は観客側から見られているだけ。俳優も観客側を本当には見ていない。こちらを見る演技をしているだけ。でもこの作品で古賀さんは、「ようこそ!」とか、ぼくはこうなんですよね、みたいなことを延々と言ってきたりするし、念力をかけてきたり、じゃんけんをしてきたりする(笑)。
山本:俳優が観客に視線を合わせてくるのはまだしも、じゃんけんをしかけてくるというのは、例えば無観客上演だと不可能なことだよね。観客側からの応答がないと成立しない。しかも、じゃんけんに勝つか負けるかが明確に舞台上で為される発話に影響を与えている、こちら側の行為が舞台上に干渉して進行を変えたということがはっきり知覚される。言い方を変えれば、いまここで見ている上演が、こちら次第でそうはならなかった可能性がすごく明確に意識されることになる。
h:その感じは、例えば第二部の「また会いましょう」ともまた全然違う。第二部では舞台と観客は一般的な演劇と同じく切れている感覚があるんだけれど、第一部はずっと前説のように、今日ここでやること、自分がいまやっていることを、こっち側にひたすら説明してくるし、観客側からの応答も迫られる。そういうあり方が、第二部にも響いてきて、作品全体として、やっぱり形式的にも内容的にも「伝える」ことが中心の問いになっていたのだと思う。第二部だって、ふたりの俳優のあいだでそれが交わされるという違いはあるけれど、自分を伝える喋り……つまり自己紹介や日記が軸になってたし。第一部を経たあとだとその受け取り方もけっこう変わる。
先取りされた発話と私という能動性
山本:第二部では、自己紹介や日記的に私的な日々を語る誰かの発話を記録して、それをもとに台詞を作っている部分が多くあったよね。日記や自己紹介する発話(それを記録したテクスト)って、それが日記や自己紹介だと知らされてなくてもそうだとわかる。そういう私的な成分を多く含んでいるというか、そのテクストの読み取りに際してそれを表現しているひとの私的な情報を、表現を受け取る側が仮構し適用していかなければならなくなるようなものとしてある。そしてそのようなテクストたちが、明らかに編集され、当人から引き剥がされた状態で発話されている。
h:それって、第二部だけじゃなくて第一部もそうだったのかな。
山本:第一部は比較的、自己紹介や日記をもとにした台詞は少なめだったと思うけれど、基本的な作り方は同じなんじゃないか。《現在は13時39分にこちらの音声を収録しております ここはスタジオでございます》とか《2月15日 収録してる 頭が動かない》みたいな台詞もあったよね。明らかに誰かが今こことは別のどこかで収録した音声(をもとにしたテクスト)を、目の前の古賀さんが平然と話している。もともとの発話が古賀さんによるものかどうかはわからないけれど(第二部では同じひとりの個人情報に由来するだろう話をふたりが共有して話すから、確実に自分とは別のひとの発話を再現していることがわかるわけだけれど)、重要なのは当人かどうか以前に、少なくともいまここで思考され自発的に発話された言葉ではないと認識できることだろう。
これと関連して、自動音声の問題がある。第一部と第二部に共通する舞台美術として、観客席側からは何が映されているのか見えない角度で置かれた一台のディスプレイがある。その付近からは、時折、自動音声で作られただろう声が流れる。断言できないけれど、第一部でのそれは、今回の「共有するビヘイビア」のもととなった『クローズド・サークル』で古賀さんと出演していた鈴鹿通儀さんの声をもとにしたものだったんじゃないかと思う。そして古賀さんは、その声に命令されるように動きを変えたり、あるいはディスプレイに向き合ってうまく会話したりもする。
ここがまたひとつポイントで……自動音声と会話する時点で、観客側からすれば、明らかにその発話は事前に用意され、会話しているふうに装われたものだと感じられる。もちろんわざわざそんなことをせずとも、演劇って、もともと先んじて用意されたテクストをそれを書いたひとではない別のひとが舞台上で発話することが、ジャンル的な基本、暗黙の了解とされている。その意味では、会話が事前に用意され、再現されているものであることになんら驚きはない(そもそもぼくらが見たプレビュー上演と概ね近いものを、この数日後の「本番」に他の人たちが見るとされていることからもそれは明らかだ)。ただ、この作品では、観客とのインタラクティブ性も含め、そのような基本、暗黙の了解そのものを上演の素材として用い、検証し、組み替えるようなギミックを大量に投入している。結果、舞台上の俳優における、ある種の自由意志や、能動的かつ即興的な発話をめぐる認識(不可能性)に、主題としての焦点があたるようになっている。
台詞のなかでもそのことは明確に触れられる。例えば第一部で何度か繰り返される以下の台詞。《言葉の集大成が言葉 ことの始まり 言葉が発生した瞬間のこと それがいつ というのはとても簡単なことでして 今です 今この 瞬間 言葉が生まれました 嘘です 何かを説明するときというのが言葉が必要なときです》。いまここで言葉が生まれているのか、あるいはずっと前に先取りされていてそれをいま言わされているだけなのか。そこに《何かを説明する》こと、つまりは「伝える」ことの問題があるとはっきり語られている。
ほかにも《話すことない》って台詞があったり、あとはSpotifyのシャッフル再生の話とかね(笑)。あれも一見するとただのばか話みたいなんだけど、自分が聞きたくて能動的に曲を選ぶのではなく、サービスの側から「あなたの聞きたい曲」が先取りされ、それを聞かされる──そういう事例のひとつだと考えられるわけだ。観客とのインタラクティブ性も、観客側からすれば、目を閉じさせられるとか、じゃんけんさせられるといった、行為の強いられ感として生じるものだろう。
こうした先取りをめぐる問題は、「戯曲とは何か」という問いを用意しつつ、上演を見るとはどういう事態なのか、何かを発し伝えてこようとする肉体を見つめ受け取ろうとするとはどういう営みなのか、といった問いにまで直結していくものだと思う。眼の前の肉体が何かを表現しているとき、それがいまこの瞬間その肉体において思考され、私自身のものとして発せられたものなのか、そうでないのか。そのような受け取りをめぐる試行錯誤として「上演」はある……そしてその延長線上に「伝える」こともあるし、(このあとしっかり話すことになるだろうけれど)会話や上演を含めた「舞台」、場をめぐる想像力の問題もあるだろう。そうした見立てのもと生み出される方法論や技術を、今回は、それによって表現しうる物語の展開を試みるのではなく、方法論や技術そのものを純粋にプレゼンテーションしている、という気がした。
もうすこし事例をあげれば……例えば字幕をめぐる話も台詞のなかにあったよね。《最近だと全てのセリフに字幕がついている 字幕をつけている 話している人が今から話すことを既に意識してその字幕に合わせて喋る 喋ることに字幕を合わせる どっちが正しいんだろう てな具合にリンクして喋る》。『クローズド・サークル』ではディスプレイに表示された字幕テキストを俳優が見ながら発話しては、リモコンで画面を操作して次のテキストに進む、というようなことをやっていたけれど、これもまさに発話の先取りの問題だよね。俳優の発話の背後に、事前に用意されたテクストが存在していることが隠されていない。今ここで即興的に発話されたものではないことが明確に示されつつ上演が進んでいく。
今回のプレビュー上演を考えるときさらに興味深いのが、俳優のひとたちがみんな印刷された戯曲を手に持って上演していたことだよね。おそらくはまだ台詞が固まりきっていないからだとは思いつつも、もしかしたら本番でもそうなのかも、と思ったりしながら見てた。
h:そうそう。特に第一部はそうかもと感じた。
山本:俳優の肉体や思考に表現の由来があるのではなく、手に持っているテキストの側にその由来がある。俳優は手にもったテキストに喋らせられているだけである、それこそ自動音声のように……。個人的に思い出すのは、ぼくらとも関係の深い、写真家/舞台作家の三野新さんが中心になって2018年に上演された「アフターフィルム:performance」。三野さんの同名映像作品をもとにした上演で、スペノのふたりも出演していたんだけど──確かそれが、ぼくがスペノのふたりを目撃した最初の機会であり、またその上演のアフタートークが、三野さんから写真集『クバへ/クバから』の制作企画を持ちかけられた瞬間でもあったわけなのだけれど──、そこでものすごく印象的だったのが、俳優がスマホをそれぞれもって台詞を発話していたことだった。三野さん由来のアイデアなのか、それともスペノからのアイデアなのかはわからない。ただ、あまりに簡単な(いわゆるリーディング公演みたいな)そのギミックだけで、発話をめぐる自由意志や由来がスマホの画面の側に奪われた肉体が演出できていたことに驚いたのを覚えてる。
h:なるほど。今回の本番はどうなるんだろう。手に持ったまま出るのかな。
山本:少なくとも、本番では英語字幕を出すらしいね。手に何も持っていなかったとしても、かなり近い状態にはなる気がする。
そこにないものを想像させられる
h:戯曲の話でもうひとつ気になったのが、台詞がいろんなところでもじられてる、ってことだった。例えば上演前に古賀さんが話しているとき、「手をクロジにして」って言うんだけど、なにそれ、と。「くの字」のことなのかなって身振りから想像して聞いてたんだけど、イントネーションも含めてよくわからなくて。このひとどこ出身なんだろうとか思ってた(笑)。ほかにも、もっと細かな言い間違いとか、噛んでるみたいな発話がたくさんあった。会場である「STスポット」について変な話が展開されるときにも、「SDスポット」とか「SPスポット」とかって言っていたし。
いったいなんだったんだろうと思って、プレビュー上演が終わった後、「なんでも質問していいですよ」って空気だったから質問したんだけど、戯曲を自動文字起こしで作ってるから細かな間違いがあるんだ、そのほうがもともとの音を残せていると考えているんだ、って回答だったんだよね。
そのときは、へーなるほどと思ったんだけど、いま、送ってもらった戯曲を見ると、こんなに間違えてるの!? って驚いた。
山本:文章で読むと本当にめちゃくちゃだよね(笑)。
h:「クロジ」は《黒字》だし、たしか上演では「アイカサ」って聞こえていたところも、戯曲では《AI傘》になってたり。でも発話されたものを聞いたときには、ふつうに理解して聞けてしまっていた。もちろん細部までぜんぶ言ってることが理解できたって感覚はなかったけれど──意味分かんないこと言ってるなーって感じだったけど(笑)──それでも、ふつうの言葉を話しているようには感じていた。それが、戯曲だけを見ると、けっこう理解できない。ただ、上演を先に見ている自分は、いま戯曲のテキストを読んでも、誤字を残してある意味不明な文が、頭の中で勝手に発話の記憶をもとに正されるからか、わりと読めちゃう。これってなんなんだろう。
山本:重要なのはやっぱり、この戯曲が、最初に書き言葉として作り出されたものじゃなくて、まず発話として生まれた、ということだと思う。発話され、録音された音声が、きれいに文章として整えられるのではなく、音の質感に由来するエラーも含んだかたちで文字化され、編集され、戯曲となっている。
この制作過程について考えるとき、例えば文字化を経ずに音源データそのままを戯曲として扱う、というやり方もありえたかとは思う。ただ、いちどテキスト化することで、複数人で共有しやすくなっただろうし、編集もしやすくなったはず。特に第二部は、ふたりの会話が緻密にコントロールされているけれど、音のままこれをやるのは困難だっただろう。
その上で、あくまで最初の発話における音の質感も重視されている。それをテキスト化の際に綺麗に整えようとすることは避けられている。
ここには、もちろん、戯曲とは書き言葉から成るものである、という既成概念へのカウンターという面も少なからずあるかと思うんだけど、それ以上に、最初の発話の瞬間にあった情報、例えば言い淀みやスリップなどをなるべく尊重する、そしてそれを戯曲にする(つまり舞台の肉体が従う先とする)という姿勢がある……と言えるのかな。
h:ただ、自動文字起こしは現状、そんなに音に正確なわけではないじゃない。言い淀みやスリップがあったからこのテキストになっているというところもあるだろうけれど、それ以上に、単純に人間の発話がうまく理解できずに(あるいは過度に正しい言葉として受け取ろうとして)変なテキスト化を行なってしまっているところがあると思う。
そういう機械的なエラーを残したまま、もういちど人間に発話させる。その声を観客として聞いたとき、わりとけっこう、ふつうに言葉として聞けてしまう。そこでの、言葉を聞く側の、聞こえた音をありえそうな言葉に補正していく機能について、わたしは考えたんだよね。これはあとから戯曲を見て思ったことではあるんだけれど。
山本:なるほどな。他者の発話をトレースすると言うと、例えば手塚夏子さんの「私的解剖実験シリーズ」を思い出す。夫の気持ちというか存在そのものを理解するために、何気ない身振りを映像に撮り、それを細部まで完全にトレースしようとする。さらにそれを複数人で共有し、演じようとする。岡田利規さんや山縣太一さんをはじめ、各所に大きな影響を及ぼした作品だけれど、スペノがやっているのは、問題意識として近いところもありつつ、明らかに違うところもある。手塚さんほどには当然精密ではなく、ざっくりしているわけだけれど、それゆえに見えるものもたくさん生じている。
スペノも発話の様子を映像で撮っていたりするかもしれないけれど、少なくとも観客からは発話の瞬間の身振り(を再現している気配)は把握できないようになっている。音声に関しても、音ひとつひとつを厳密に表記しようとするならそういう筆記法はこの世の中に存在しているわけだけれど、そうではなくあくまで自動文字起こしを経由させ、いわゆる自然言語でテキスト化した上で、俳優に発話させている。
h:しかも自動文字起こしを使っているということは観客からすればわからない、ということが重要だと思う。ただの聞き間違いかもとか、意図的に言葉を崩しているのかもと思ったりするだけで。
山本:なるほどな。「SDスポット」とかってはっきり言われると、何かしら意図のある言い換えなのかなと思うよね。ぼくは「STスポット」に関する明らかに嘘っぱちな話をしていることもあって、わざと別の名前にずらして言ってるのかと思って聞いてた。
h:あの話に出てくる「佐藤さん」って、ほんとにいるの? 穴を掘ってここを作ったってほんとなの? とか……お前の言ってることは本当なのかどうなのかはっきりしろ、みたいな瞬間が何度も起こるよね。
山本:胡散臭さがすごい。それはテキストだけの問題じゃなくて、古賀さんの演技体の特異性から立ち上がるものでもあると思う。いま目の前で考え発話しているようでもあり、観客と対話しているようでもあり、でも明らかに自分とは別の場所に由来を抱えて喋らせられてもいる、その絶妙な演技のバランスから生じる胡散臭さ。
h:そうね、すごく面白かった。胡散臭いというと悪いニュアンスが強くなっちゃうけど(笑)。
山本:でも、胡散臭さとしか言いようがない質感がある(笑)。
h:言ってる内容をどこまで真に受けて聞いて良いのかわからなくなるんだけど、でも観劇中は、やっぱり意図とかを汲み取ろうとしちゃう。それでけっこう辻褄が合った気にもなるし。でも、実際には、別に「STスポット」をあえて「SPスポット」と言い換えて言っていたわけじゃなくて、ずっと「STスポット」に関する話をしていただけなんでしょう? ただの文字起こしの結果なので……みたいな。悔しいよね、自分のなかの相手を汲み取る能力みたいなものを無駄に使わされている感じがして(笑)。機械のエラーをわたしに押し付けないでよ、って。
山本:そこで生じる「ただの機械的な情報にも人間的な意味や意図を汲み取ってしまえる」ということもまた、肉体に能動性を見るかどうかに関わる話でもあるわけだよね。
h:そうそう。
山本:いったん自動文字起こしを挟むことで、表現における由来、根拠を、最初のひとの発話にのみ還元できるものではないようにしている、と。そういえば『クローズド・サークル』でも似たような方法が取られていた。テクストや上演の流れが、「バックギャモン」っていうテーブルゲームのルール・進行にのっとって決められていたのね。そこでもやっぱり観客側は「なんでここでこの発話が為されたんだろう」といろいろ考えさせられるんだけれど、蓋を開ければ、「ゲームがこうなっているからですよ」とあっさり返されてしまうわけだ。何かしらの物語や意図を探ろうとするのに、その先にあるのはそれ自体としては何の意味も持たないただのルール(の遂行・上演)でしかない。
こういうところから、例えばぼくなんかは、大岩雄典さんのインスタレーション作品を連想したりする。大岩さんも、(大岩さんそのものとイコールで結ばれがちな)特定の作家性に作品が還元されないよう、明確なゲームルールを露骨に提示して、観客側からの意図の汲み取りを不全にしたりする。さらに、観客側の行為を戯曲や美術などでもって先取りしてしまう、そこで起こる不快感なども含めて作品の質にしていたりする。スペノと大岩さんはやっていることが近い、とも言えるかもだけど、それ以上に、上演というものそれ自体が備えている諸々をストイックに問おうとすると必然的にそういう作品の作り方になる、って話だろうなと理解している。
ちなみに、音に関わる操作は、第一部では「おやすみんみんぜみ」みたいな言葉遊びに関する話にまで進んでいったけれど、これもまた、音が依拠するルールをもとになかば自動的に発生する表現にひとがいろいろな情動を勝手に立ち上げてしまうという話だと思う。
音の問題を扱うとこういう議論展開になることはよくあって、例えば詩歌の形式をめぐっても同様のことが生じる。短歌の定型、つまり57577にのっとって音が並べられていき、ひとつの表現が作られるとき、そこにある情動や思考は音の醸す言語的な意味に由来するものなのか、作者に由来するのか、あるいは57577というリズムに由来するのか。だれがその表現にとっての主体であり、原因なのか。そこに埋め込まれていると読み手側が感じてしまった情動や思考は、果たしてどこからやってきているのか? なんてね。
そういったことが、今回の作品では、戯曲と上演を考える上での一例としてさりげなく提示されている。全編にわたって話されている内容はぺらぺらなんだけど、それらがいずれも問いを鮮明化することにうまく寄与させられている、と言っていたのはこういうようなところのこと。
例えばマスクの奥での口の動きを想像させるような身振りや台詞があったけれど、あれも同じ。一見するとどうでもいい細部だけれど、観客側からすれば、知覚情報としては得られていない空間(マスクの向こう側)を自分がいつのまにか想像してしまっている、そのことを自然と自覚させられる一例となっている。
このまま、空間をめぐる想像の話に進めば……第二部でよりはっきり扱われることだけれど、舞台上の発話によって観客がこことは別の空間を想像させられてしまうという事態は、いろいろな角度から展開されていたよね。「STスポット」をめぐる話も、いまここの舞台をめぐる想像力に関わるものだと言えるし、それこそ言葉遊びの話のとき、古賀さんが、舞台奥の出入り口に立って、こちらからは見えない壁の向こう側に向けて話していたのも、そうした想像力への注意をシンプルに喚起する演出だったと思う。
h:あそこは今回の作品のなかで一番笑えるところだったよね。「おはヨーグルト」は「おはよう」と「ヨーグルト」の組み合わせが最高ですよね、朝と爽やかな感じがいいんですよとか(笑)。そういうことを舞台の裏に向けて話しながら、ときどき観客側を見る。その様子も面白い。あれって、観客が笑ってるかどうか確認しているみたいだったよね。反応をうかがってるのかな、っていう。なのに裏に向けて話している。それまでの前説みたいにがんがん舞台上から話しかけてくるのとの対比もあって、不思議な印象だったな。
ダンスと共有
h:わたしが「伝える」ということについて考えたのは、主には第二部を通じてだった。
第二部は、すごく簡単に言ってしまえば、渚さんと西井さんというふたりの俳優が舞台上で話している。でも、ふつうの会話とかではなくて、一方的に話したり、同時に別々のことを話したりしている。
山本:バーっとまくし立てるような感じでね。
h:でも、聞いていて、ぜんぜん意味がわからないとかではない。ふたりだからぎりぎり何を話しているかは掴めたりする。そして、ときどき「わかった?」「わかった」みたいなやり取りがあって、話が急に止まる。逆に言えば、話が止まるその直前に、ふたりが応答しあう瞬間が訪れる。観客からすると、「あれ? やっぱり話してた? お互いわかりあえてたの?」と思うわけだよね(笑)。でも話が再開すると、またお互いがぜんぜん違うことを言っていたりする。この、お互いぜんぜん別の話をしているのに時々お互いに伝えあえていると錯覚させられるような瞬間が生まれる、これってなんなんだろうと考えたんだよね。
山本:それは、ふたりの俳優のあいだで何かが伝えあえている、ということ? それとも、俳優たちから観客側に何かが伝えられてしまっている、ということ?
h:両方。伝わっていないなと感じつつ、でも伝わっているとも感じる、じゃあそもそも「伝わらない」ってなんなの、とか。
山本:なるほど。それは第一部でいったん明晰に言語化されつつ展開されていたことでもあるよね。あらためてあなたが引いていたところを引けば──《根底に共通するのは何かを伝えるということ しかもそれは矢印としては伝えるというベクトルが向いているということが全てで共通していると思います ダンスの工程とか なぜこのダンスが生まれたか 紹介する 説明とか 紹介っていうのがこの共有するbehaviorを説明する上で正しい伝え方だと思っていて 今説明の説明をしてる だから何者であるとかとか どういう存在であるかとかはある種関係なくて この現象を伝えようとしている「私」とそれを聞こうとしてくれている「あなた」このダンスを伝えます このダンスの背景を伝えます みたいな》、とか。
h:まあその意味では、素直だよね、わたしは。「伝える」がテーマだと言われて、その通り受け取ってるんだから。
山本:でもこの作品自体、そういう意味での明晰さ、露骨さがあると思うよ。何かを隠したりこっそり表現したりするのではなく、はっきりと「ここに問題があるんです」と開示した上でやっているというか。
h:第二部は第一部で展開されたテーマがより実践的に展開されているのかな。ふたりのあいだのやりとりには、わりとふつうに会話として成立しているところもある。伝わってるかも、とかではなく、あきらかにふつうにやり取りしているところ。でもすぐにまた、すれちがいになる。だから、「伝わってる」「伝わってない」をめぐるこちらの認識もどんどん揺らいでいく。そこが面白い。
山本:また第一部の話にもどっちゃうけど、もともと「共有するビヘイビア」が2018年と2019年に上演されたときには、ダンスの背後にある制作過程などを観客に共有するという意図をもった作品だったということは、台詞のなかでも明言されている通り、やはり重要なことのような気がする。
ものすごくざっくりした話になるけれど、ダンスって、踊る側からするとものすごくいろいろな感覚や思考を展開していたりするけれど、それを見る側は、なんか動いて表現してるっぽいな、程度の解像度でしか捉えられていないことが多いと思う。踊っている肉体を外から視覚的に認識することはできるし、そこでの身振りを通じて踊っている肉体か、あるいはそれが依拠しているコレオグラフを作成したひとが何かしらを表現しようとしていることまではわかる。でもそれが何なのかまでには至らぬまま──ブラックボックス化したまま──見終わってしまう。
肉体の身振りを見て、それが由来している感覚や思考を把握するというのは実のところけっこう難しい。熱さを受けての条件反射とかなら、大半の肉体は同様の動きをするだろう。白鳥の見た目を真似して踊る、とかもまだわかりやすい。でも、例えば「生」を表現して下さい、みたいに言われると、みんな思い思いの動きをするほかないだろう。そうして為された表現から、その由来を明確に逆算することは、身振りがひどく定型的なものである場合を除けば、かなり難しいだろうと思う。そしていわゆるダンス作品の場合、条件反射も複雑な表現もひっくるめて編集し、構成していくわけだから、さらにことは複雑になっていく。
そうしたなかで、2018年と2019年バージョンの「共有するビヘイビア」では、ダンスを作る過程での議論と、ダンスそのものを、ともに編集・構成し、ひとつの作品のなかで展開する。つまりダンスだけを提示するのではなく、その背後にあるものの開示・共有込みで観客に見せていく。自然と作品は、ダンスをそれ足らしめている必然性、発端のようなものの言語化と伝達をめぐるものにもなっていく(こうやって語っていくと、いぬのせなか座が自分らの詩や小説を、その制作過程や背後の思考をめぐる座談会(しかも何重にも編集・構成されたそれ)とともに一冊にまとめて発表していたのと、やり方として近かったのだろうなと感じる。実際、実はぼくはスペノを見始めるだいぶ前から、いぬのせなか座とスペノは近いんじゃないかとたびたび周りから言われ、気になっていた……)。
ついでに言えば、2022年7月に見た『ストリート リプレイ ミュージック バランス』も、ダンスを構成する複数の要素・要因をひとつひとつ丁寧に観客に見せては並置していき、掛け合わせ、厚みのあるダンスの経験を徐々に作っていく作品だった。ものすごく教育的かつロジカルなプロセスを踏むことで、身振りはその場で生み出された即興的なものとしてではなく、漠然とした謎でもなく、厳密に計算され仕組まれた身振りとして把握できるようになっていく。さらにはその身振りが作り出す周囲の空間への想像力の推移も、クリアに観客側に自覚されるようになるんだよね。
「共有するビヘイビア」は、すでに何度も触れている通り『クローズド・サークル』という作品に発展するんだけれど、そこではいわゆるダンス的な成分はぐっと減り、ふたりの俳優による発話が中心になる。そしてその先に、今回の作品があるわけだ。つまりは発話・会話にすごく重きを置いている今回の作品の背景に、ダンスとその共有をめぐる問題意識や蓄積があるということ……スペノの経歴を知っているなら当たり前のことかもしれないけれど……このことはあらためて重要な気がする。眼の前の肉体が何に依拠して発話し、身振りを行なっているのか。それをめぐる観客側の認識とはどのようなものか。舞台と観客のあいだの「伝える」という関係はいったい何なのか。それら全体を取り巻く空間とは何なのか。
……ということを踏まえた上での(笑)、第二部における「会話」の問題、だよね。
破壊的テクストと共有される場
山本:第二部で重要なポイントのひとつに、テキストの反復的共有がある。具体的には、例えば岸田國士で卒論を書いたという話を俳優ふたりともが時間を置いてそれぞれ同じように発話する。これって観客側の認識で言えば、ある種の役柄の交代のように感じられる事態なんだけれど、もう少し踏み込んでいえば、そのテキストを文字起こしする前の自己紹介的な発話が俳優ふたりに共有されているわけだよね。しかもひとりの発話がふたりに共有されているということは、少なくともそのうちのひとりは、自分とは別の者が私的な情報をめぐるものとして為した発話を再現していることになる。ひとりではなくふたりで話すことで、そのような認識に自然と無理なく観客側が至るようになっている。
h:しかもそれは、岸田國士みたいな固有名詞だけじゃなくて、いぬがかわいいとか、好きな映画はなんですか、みたいな台詞を起点にしても把握できる。つまりかなりの頻度で、ふたりがひとつの人物を演じているようだというのがわかる。
もうひとつ謎なのは、第二部でも第一部と同じく舞台上に、こちらからは何が映っているのかわからない角度でディスプレイが置かれているんだけれど、そこから声がすると、舞台上のふたりが異様な驚き方をしながら、舞台奥のふたつの出入り口にそれぞれすっぽり収まっていくところ。後ろ向きに一気に激しくさがっていって、痛みのようなものを感じているふうに見える。やめてほしいというか、嫌がっているというか、こわがっているというか……いずれにせよプラスの感情じゃないよね。そうした場面が何度か繰り返される。あれはなんなんだろう。
山本:現象としてはわかりやすくはあるんだけれどね。
h:そう、何かしらのルールがあるということはよくわかる。「ディスプレイが喋ったら嫌がる」というね。まあそれも徐々に解体されるわけだけど。
他にも、身振りに関するルールがいくつかあるようなのは認識できる。例えば、「どういうところに住んでたんですか」みたいに聞かれたら、台にのぼってそれに答える、とか……その意図まではわからないし、そもそも把握が合っているかどうかもわからないんだけれど、何かしらここにはルールが働いているんだなとはわかる。そしてそれは、ふたりの「会話」からすれば、すごく安心できるものとしてあるなと感じる。
ふたりは基本的に話している内容がずれていて、同じ舞台上にいるにもかかわらず、お互い隔絶され、力の及ばない場所にいるように感じられる。でも、さっきも言ったように、あるとき急に、「そうですよね」「はい」みたいな応酬がくる。それが、見ていてすごくこわいんだよね。こんなにそばにいるのに交われないんだ、伝えあえないんだ、というところから、急に会話が成立したようになって、また離れていく。その伝わらなさとか、伝わったかと思えばまた離れていくこわさと比べると、身振りに関するルールは、どこか安心できるものがあった。
……というか、今気づいたけれど、第二部の戯曲、やばくない?(笑)けっこうちゃんとした台詞だと思ってたけれど、文章で見ると、第一部よりもさらに意味わかんない。《チキン鶏肉ねんとりこしょっぱい》って、なに。
山本:これは……(笑)。
h:ふたりが同時に話すから聞き取れないんだと思ってたけれど、ほんとに意味わかんないこと言ってたんじゃん(笑)。たったふたりでも同時に話されると無理なんだ、って思ってたけど、これじゃそもそも聞き取れるわけがなかった。
山本 なるほどなあ。
h:ひとりひとりで喋っているときの台詞は、当たり前だけれど聞き取れるわけだし、上演中は内容も含めて理解できてる気になってた。でも戯曲を見ると、かなりへんだったことがわかる。例えばこことか……。
N1 メープルシロップは振りつき
N2 もう学びっていう名前なんですよ
N1 そうなんですか 珍しいですね
N2 違う弓田 すごい お母さんのおねちゃんが真弓さんです いとこが愛美ちゃーんでしたね
N1 うん なっちゃん うんちゃんって言われます でもまだちゃんは 飲み物が好きNO中のビルオーナーとコーヒーかな
N2 コーヒーが好きです
この場面、はっきり覚えてるけど、《愛美ちゃーん》とかは聞き取れるけれど《なっちゃん うんちゃんって言われます》とかは「ん? なんだろう」くらいまでしか理解できない。《飲み物が好きNO中のビルオーナーとコーヒーかな》とかになるとぜんぜんわからなかった。でも次に《コーヒーが好きです》と来ると、急に会話として聞こえてくる……。
上演中は、ひとりひとりはちゃんとそれぞれで理解できるようなことを喋ってて、でも同時に話していたり台詞が意図的にすれ違わされていたりするから理解が追いつかないだけ、と思っちゃうけど、戯曲を見ると、そもそも伝わることなんて最初から喋ってなくて、互いに、それから観客にも伝える気がなかったんじゃん、と思う。何かがあるわけじゃない、何もないことを言われていただけだったのに、上演である以上──というかひとが前で言葉を喋っている以上──そこにはなにかがあると思わされてしまっている。これは、やっぱりこわいことだよね。日常も実はこんなものだと言われている気もしたし。
山本:破壊的な文章でもって「聞こえさせていない」ところと、会話としても意味内容としても「聞こえさせている」ところが、ものすごくうまくレイアウトされているよね。ずっと会話が成立しない、意味がわからない、とかじゃなくて、わかるところとわからないところのリズムがコントロールされている。
h:そうだね、されてた。テキストそのものもだし、発話でも、ふたりのあいだでうまく間を置いたりしていた。「聞こえて……る?」みたいな(笑)。
山本:そうそう。テキスト内外のいろいろな要素を駆使して、会話の成立(不)可能性を精密に演出している。視線の向きや、どこでどう頷くかとか。音楽のリズムを取っているときの頷きと相槌の頷きが同期させられる、みたいなこともあったと思う。
あと、空間の共有……土地や風景の描写はもちろんだけれど、例えば《柴が居ますね》とか《どら焼き》とかみたいに特定の対象をフィクショナルに名指すような発話はけっこうな頻度でふたりのあいだで共有され、ともに立つ場を形成する。その瞬間、会話が成立したりする(そのように感じられたりする)んだけれど、とはいえ仮構される対象の位置も、お互い想定している場所がずれていることが明らかだったりするから、すぐに崩れていってしまう。
ほかにも、「それ」「これ」「あれ」みたいな指示代名詞は、会話の成立(をめぐる知覚)を促していたよね。「私」もそうだし、あとはやっぱり名詞の反復は最たるものだったと思う。一方、同じく人物名でもってふたりのあいだのずれが強調されたりもするわけだけれど。そういう細部のコントロールがすごい。
さらにもうひとつだけ加えると、ディスプレイに向かって「音楽をこの部屋に流してほしい」って言う場面があったよね。すると実際に音楽が流れる。それは舞台上のふたりにも、観客席にも、さらに言えば会場外の廊下を歩いているひとたちにももしかしたら聞こえているかもしれないものだ。これまで触れてきたようなどれよりも、はるかに強い共有、同期の礎としてある。舞台美術を指さして「これ」と言うときがあったと思うけど、それよりも強力なものだと思う。
h:伝わってるんだな、と感じられる。
山本:でも、次に発話されるのは《違う ちょっと違う ちょっとたぶん違う》。やはりだけれど、また共同の場は崩れる……このあたりの半ば露骨とも言える展開の塩梅が、うまいんだよなあ。
こういうことの積み重ねが、二つの肉体のあいだの共通の場をめぐる判定基準の検証となり、すなわち「会話」というもの、「伝える」ということの判定基準の検証となり、さらにはある肉体における自由意志や思考をめぐる判定基準の検証となる……そしてもちろん、第一部をめぐって話していたような、戯曲の問題にもなっていく。戯曲もいわば、舞台上の複数の肉体が帰属する共同の場の一種だよね。ひとつの同じ戯曲を共有できているということは、ひとつの場を共有できているということであり、そこには(一般的な意味かどうかとは別に、肉体と肉体が同じ地平を共有して関わり合うという意味で)会話が成立するだろう。言い換えれば、そのような対象であるからこそ、この作品において戯曲は、音楽と同じように「違う」ものとみなされ、自動文字起こしを挟んでエラーを大量に食い込ませられたり、もととなる発話主体を置いたりして、単一の書き手に統合されないように操作されている。
こうした諸々が、上演という表現形式における最たる素材としての、観客と舞台のあいだに生じる想像力に関わるものとして、一気に貫かれるというか、ぜんぶ同じ問題なんですよと示されているような感覚があったな。
そしてその上で、舞台そのものとは別で収録され戯曲の素材とされているところの、日記的な発話とはいったいなんなのか、というところにまで返っていくのかもしれない。
話すことのなさと方法
山本:話し損ねたことを最後に手短に並べておくと……第二部での《歩きたくなったら歩いてもらって》という台詞(続けて、言われた側が歩き始める)も印象的だった。まさに能動受動、行為の由来の問題だよね。しかもこの台詞も、間を置いてもうひとりが同じく発話することになる。この交換可能性。
あとはドッペルゲンガーのモチーフも、第一部・第二部共通のものとしてあったよね。第二部で言うと、例えばここ。《この前すごいおばあちゃんに似てる人がいたんですね おばあちゃんは髪型がすごい 毎日パーマを当てに行ってたんですよ 毎日当てに行ってたんだけど その人はショートカットでピンクの髪型だったのね ベリーショートだけど 他はどう見てもおばあちゃんにそっくりだった いきなり話しかけてもちょっとびっくりされるかなと思って 普通に後をつけてたんだけど その人がすごいこっちをすごい伺ってきてたから 会釈しようと思って釈して通り過ぎたんだけど その通り過ぎた瞬間に「私」だって思ったんですね》。
h:ああ! あったあった。それすごくこわかった。しかもディスプレイに向けて話してた気がする。すごく嫌だった。第一部にも似たようなことがあったね。
山本:どこだったっけ……いま(2023/03/16)はまだ記録映像が届いてないから、戯曲のデータを検索しつつ記憶をたどることしかできないのだけれど……あ、ここだね。
h:《出会いの場というのは どのような場所だとお考えでしょうか 例えば公園 例えば学校 例えば道野途中 駅のホームでした 別の線と線が交わるところ 大きな駅のホームでした そこで 年老いた「自分」と出会いました 姿は全然今とは全く似てませんでした でも直感で「自分」だということが認識できました どっちとも言わず話していました 内容としてはゲンキーみたいな 体とか壊してないのとか 最近楽しかったこと何 ほとんど久しぶりに会った友達と会ったときに話すような内容ばっかりで 何故なら深入りして何かを話すことが結構怖かった だから 当たり障りのないような 割とライトめな会話をメインで話してた》。
山本:そして自動音声が《話すことない》と返事するのか……。この作品全体における「話すことない」っぽさはすごいよね。
h:あんまり意味ないもんね(笑)。
山本:にもかかわらず、大量に喋り続けてて、それを観客は聞こうとしちゃう。聞こうとさせられちゃうような演出や演技、テクストの技術がすごくある。
h:あと、第一部と比べると第二部のほうは、すごく自制的というか、自分を抑えて喋ってる印象がすごくあった。言葉をここに置くよ? 置くよ? みたいな丁寧さがあったというか。それは演出の複雑さ、意識し実現しなくちゃいけないことの多さから来るものでもあると思うんだけれど、その上で、すごく抑制されている感覚が全体にある。だからこそ、ディスプレイから自動音声が聞こえた瞬間、ふたりがわーって驚いて激しく動くのに対しても、すごくこわく感じられる。ものすごく強い感情の発露に見えるから。
山本:そういう抑揚を作るのが、ほんとにうまい。
h:だってさ、ちょっと眠くなりそうなときにそういうことをやってくるでしょう?
山本:確かに(笑)。
h:そういううまさもあった。やっぱり情報量が多いから頭がぼーっとしてきちゃうしすごく疲れるんだけど、いいタイミングですごく明確な出来事が起こる。そういうところもすごく面白い。
山本:あと、最後にもう一個だけ。ちょっとメタ的な話というか、作品全体を比喩的に表現している箇所の話になっちゃうんだけれど……。
h:「0.5人」の話?
山本:ああ、それも重要だね。それと絡むようでもあることとして、第二部の冒頭、「念力暗転」の話から始まるんだけれど、西井さんが前に出てきて念力暗転を実演するような振る舞いをする一方、同時に少し後ろで渚さんがその様子を外から描写するような話をする。ひとりがひとりをはっきり語って記述する場面というのは、ここくらいなのかな……ここで示される関係性はすごく印象的で、作品全体を貫くイメージにもなるところだったなと思う。もう何度も触れてきているけれど、なにかに先取りされている感覚もあるし、私が私を語っている、ある種の分身関係の発露というような感覚もある。なんというか、最晩年のベケットを思わせるところもある。
またその話が念力暗転の方法の説明をめぐるものだったということも、極めて重要だった気がする。この作品の軸は方法のプレゼンテーションなんだ、ということが意識付けられたというか。つまりはエピソードや個々人の情動などではなく、異なる人物、異なる場所で転用可能、反復可能な何かをめぐるものなんだ、と。《知ってるのは 舞台上に1人 人が立っていて 手をかざして それ見てる人がまぶたを閉じるっていうやつを知ってるんですけど》って渚さんが西井さんに向けて語るとき、それは西井さんがいま演じている誰か個人を描写しているのではなく、あくまで念力暗転の方法、具体的なプロセスの話をしているだけなのね。でもそれが、目の前に立っているひとの描写にも聞こえるんだよ。この妙な状態が、すごくおもしろいし、今日話してきたこと全体をあらわしているようにも個人的に感じられる。
で、結局、「本人たち」ってなんなのか、ってところだけれど、上演と生の根幹にある、特定の「舞台」に限られない、極めて日常的で匿名的かつ反復可能な形式……それがつまりは伝達をめぐる方法であり、演出であり、社会の構成単位であり、新たな意味での戯曲である、のか……。
2023/03/16-19
※プレビュー上演は2023年3月15日に「STスポット」にて非公開で行われた。
※引用したテクストは、いずれも2023年3月16日にスペースノットブランクより共有されたプレビュー上演時の戯曲データに由来する。
| 山本浩貴 Hiroki Yamamoto Web/Twitter |
| 1992年生。言語表現・レイアウト。小説や詩やパフォーマンス作品の制作、書物・印刷物のデザインや企画・編集、芸術全般の批評などを通じて、〈私が私であること〉の表現あるいは〈私の死後〉に向けた教育の可能性について共同かつ日常的に考えるための方法や必然性を検討・実践している。主な小説に「無断と土」(鈴木一平との共著、『異常論文』ならびに『ベストSF2022』掲載)、主な批評に「死の投影者による国家と死」(『ユリイカ』2022年9月号 特集=Jホラーの現在)、主なデザインに「クイック・ジャパン」(159号よりアートディレクター)、主な企画・編集に『早稲田文学』2021年秋号(特集=ホラーのリアリティ)。2015年より主宰する「いぬのせなか座」は、小説や詩の実作者からなる制作集団・出版版元として、各種媒体への寄稿・インタビュー掲載のほか、パフォーマンスやワークショップの実施、企画・編集・デザイン・流通を一貫して行なう出版事業の運営など多方面で活動したのち、2021年末をもって第一期終了、現在は山本のみを固定メンバーとした流動的なかたちをとっている。理論・批評の単著を2023年刊行予定。 |
| h |
| 小説の制作のほか、「いぬのせなか座」のメンバーとして山本浩貴とともに書物・印刷物のデザイン、パフォーマンスの制作を行なう。主なデザインに田恭大『光と私語』(いぬのせなか座叢書3)、主な小説に「すべての少年」、「盆のこと」(『いぬのせなか座2号』)、『2018.4』『六月二一日』(いずれもいぬのせなか座)など。 |
本人たち
イントロダクション:植村朔也
レビュー
本人たち|山本浩貴+h(いぬのせなか座):伝達の成立(不)可能性を方法化する──小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『本人たち』プレビュー上演
本人たち|東京はるかに|舞台よ物体であれ:スペースノットブランク『本人たち』『オブジェクト(ワークインプログレス)』評
本人たち|鴻池留衣:この世が舞台であることと、舞台がこの世であること
本人たち|稲葉賀恵:かかわりあうことの奇妙
本人たちを見た本人たちによる本人たちのレビュー
本人たち|神田茉莉乃:見ること、見られること
本人たち|高橋慧丞:、と(彼)(彼女)(ら)は言う
本人たち|長沼航:1でも2でも群れでいて
本人たち|中本憲利:さらに新たなる本人たちに向かって