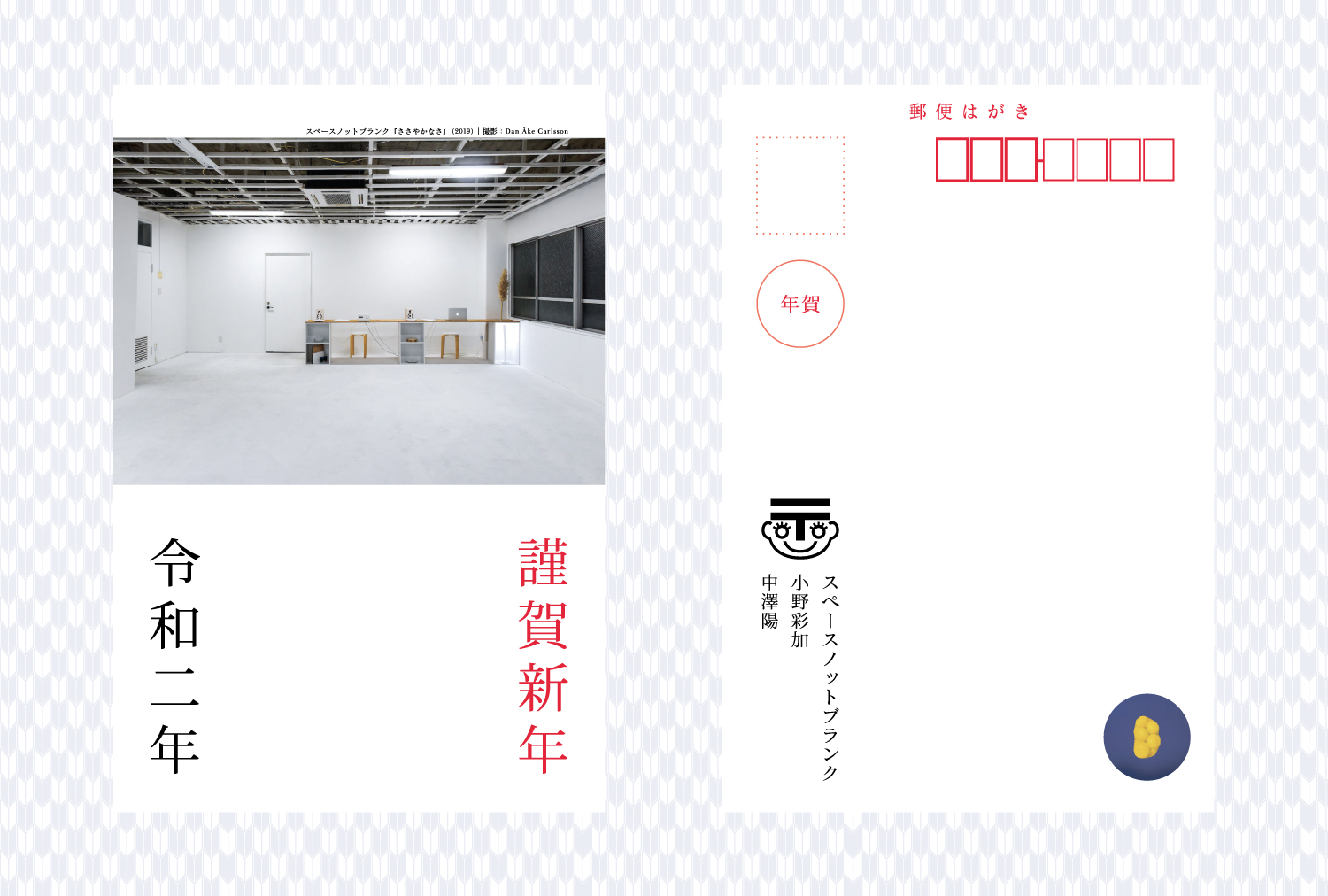東京はるかにの植村です。
スペースノットブランクの新作『ウエア』上演に際し、保存記録を務めますわたくしが、原作を書いた池田亮さんに直接お話しをお伺いし、インタビューとしてまとめさせていただきました。
2万字を超えるインタビューとなりました。
また、インタビュー内容に作品のネタバレを含みますので、ご観劇をお考えの方は、観劇前に読むか、観劇後に読むか、ご自身の判断でお読みいただければ幸いです。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

池田亮 いけだ・りょう
舞台、美術、映像を作る団体〈ゆうめい〉代表。1992年8月31日生まれ。脚本、演出から俳優、彫刻から模型、小道具から大道具、映像まで手掛ける。2019年にMITAKA“Next”Selection 20thにて『姿』を上演。近年ではアニメ『ウマ娘』『チャレンジ1ねんせい』『けだまのゴンじろー』やYouTubeチャンネル企画の脚本を担う。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村朔也(以下、植村) 池田さんはご自身の記憶に取材して作品を書かれる印象が強いですが、『ウエア』はそうした予想を裏切るものでした。
池田亮(以下、池田) そうですね笑。僕はもともと彫刻とかをやってて、彫刻だと一人でものを作れるっていう意識があったから、だいぶイメージで作れたりするんですね。ただ、舞台となった場合はみんなで作るっていうことをやりたいと自分は思っていて。ゆうめいはいろんな人が関わる中で最初の共通を探そうみたいなところがあって、それで実体験や、取材してきた現実の根強い部分から立ち上げてくるっていうことを意識しているんです。三月にやる『ゆうめいの座標軸』ってやつもほぼほぼ自分の実体験とかからかなり引っ張ってきて作られてるんですけど、実際僕が自分一人の時って、イメージとかフィクションの方でだいぶ作っちゃったりとかして。フィクションは現実がスタートとしてあるけど、そこからどんどんずれてくみたいな、現実からどんどん離れてしまうみたいなのを自分一人だと作ってしまうので、ゆうめいの作る作品と『ウエア』はスタートの意識からだいぶ違うって感じですね。
植村 今後の具体的な展望はおありですか?
池田 今回池田亮っていう名前出して原作やったのが初めてな気がしてて。今までは全く名前は出さずに、誰もいないところのメーリスに勝手に送りまくったりとか、匿名を使って『電車男』みたいなことをひたすらやってきたので。嘘ついて、まったく嘘なのに、ほんとリアルに匿名な人からあっちも嘘かもとかわからないけどこっちにレスポンスしてくるっていう感じ。それでなんとなくな虚構を作ってるみたいな。それが例えばまとめサイトだったりにまとめられると、嘘からスタートしてるのにすごいリアルな返答をしてくれる人だったり、嘘だってわかってるかわかってないかわかんないけど冗談めいた返答をしてくるみたいな、なんかそういうある種すごい『ウエア』の世界に近いようなことばっかりやってきたので、そういう意味では今回自分の名前出すっていうのは初めてだなって思います。IPがばれたじゃないですけど笑。
植村 『ウエア』のLINEグループで「最高傑作です」と自信ありげにおっしゃっていたのが印象的でした。
池田 今までずっと匿名で作ることを僕は沢山してきて。2ちゃんねるでいうところの「名無しさん」みたいな、名前のない状態から自分の表現をしていくっていうのが今の自分にとっての結構なストライクゾーンみたいな。名前があるものって結局作者は誰ってところにだいぶ持ってかれちゃうと思うんですよ。自分だけの自分だけしか知らないものを作りたいって野望は凄くあったりしますね。これを書いたのは池田だと分からない作品を作りたいっていう。
植村 普通は自分一人で作る時の方が個性を出したいものだと思うのですが、池田さんは一人の方が匿名的な方向に向かわれるわけですか。
池田 たぶんそんな感じはありますね。『ウエア』も自分の名前を出さずにどう書くかっていう意味で、メーリングリストにずっと名前を変えた実在していないアカウントからメールを送り続けて「これ一体だれが送ってるんだろう」っていう。そこに作者の名前が出ないってことを凄い意識しながら作ってて。スペースノットブランクの二人が話してたのが、原作で名前を出すっていうこととか、いろんな周りの人と一緒に作るっていうことをあまり意識しないで、一人だけのものを作ればいいっていう。なんでまあ一応名前は出るけどそこはもう抜きにしてやろうって思って作った。なんで個性が出るっちゃ出てるんじゃないかなあと思う。
植村 確かにそうですね。けれど個性を出しながらも匿名性を志向なさるわけで、その原動力はなんなのでしょう。
池田 好みなんですけど、自分がなんかの作品を観た時に、作者の名前が出ていたらちょっと若干懐疑してしまうっていうか。作られたものっていうか、作者の方まで探りたくなっちゃうんですけど、それだと意図だったり発想だったり、作品とは別のところに行くなっていう感じがあるんですけど、逆に名前がなくていったいこれどういう人が書いたんだろうっていうと、いろんなことが想像できる。知名度だったり価値だったり助成金が取れるか取れないかみたいなそういうこととか、そういうところ抜きにしてやってるものに僕はすごい価値があるなみたいなことを。純粋に出てるなって感じがすごいするんですよね。
植村 池田さんは東京藝術大学のご出身でしたね。
池田 でも全然通ってなかったです。多分五回くらいしか。院の三年間で五回ですかね。一年留年しちゃって、城崎のアートセンターってところで卒業制作をしてた。一年から二年の進級の時は今まで大学外でやってた活動をプレゼンして「卒業制作こんなことやろうと思ってます」って言ったら特別に進級させてもらって、で、卒業制作はほんともうテキト―に作っちゃって笑、コンセプトも嘘ででっち上げて、そしたら信じてくれて申し訳ないなってほんとに。他の人達は一年二年くらいじっくりかけて作ってたのに自分は三時間くらいでもうホームセンターで勝手にテキト―な感じで作っちゃったやつで、コンセプトはその場ででっちあげたのに、そしたら教授的には「なるほどね」って言ってくれたんで。
植村 コンセプトって本当に嘘で作れるものですもんね。
池田 本当に嘘で作れるなと思いました。びっくりしました本当に。三時間で作ったやつは木で本当にテキト―な箱を作って、一輪車を乗っけて、で、テキト―に端材をくっつけたやつなんですけど、でっち上げたコンセプトは「親戚に子供がいて、子供が描いた絵を子供と描いた時間でこっちも立体として成立させる」っていう。
植村 もっと観念的な理屈の上でのでっちあげかと思ってましたけど、それは本当にただの嘘ですね笑。
池田 それで子供の教育とかにくっつけたんですけど。出来るものと、自分が何年間生きてきた上でのそれを立体として、で子供が遊具を描いたから僕も遊べる遊具を作りましたみたいな。
植村 子供はそもそも存在しないわけですよね笑。
池田 そうですね普通にいないです。で子供がこういう風に遊びましたとか嘘ついて、そしたら「なるほど、それは面白いねー」って笑。そしたら教授が信じちゃって面白い面白いって言って単位くれて。芸術ってマジ嘘っぱちだなーって思いましたほんとに。他の人とかもほんと一年間くらいかけてすごいでっかい大理石とか使って五メートルくらいのめっちゃでかい立派なやつとか作ってるんですけど、そういうの作ってる人に、自分のこと褒めてくれた教授が「ちょっとこれ見たことあるんだけどなぁ」みたいな事を言ってるときは本当にもう。ほんとテキト―な世界だなあって。有り難いなあと思いつつちょっと申し訳ないなあ、基本でっちあげなんだなあと思いました。
植村 『ウエア』は匿名性はありながらも、文章の書き手はどれも池田さん以外の誰でもないという解釈にも開かれたテキストですよね。そこが魅力的と感じました。
池田 確かにそれ(その解釈)含まれていい気がしますね。ゆうめいと全然違うってことがある種の匿名性になるのかなとか思って。原作と自分どっちが本当なのかわからないけど、どっちが本当なのか、それともまた別の人がいて別の人が書いているのかじゃないですけど、ちょっとこう自分を分散させたいなみたいな意味がすごいあったような気がしますね。自分をすごい分散させて、読んでる人が「書いた人が池田亮だから全部池田亮が書いたんだな」って思ってもらってもいいと同時に、でも自分のこと知ってる人ってやっぱ大抵ゆうめいの作品を知ってたりとかしてるんで、別のこういうものも作れるんだじゃないけど、全然自分の思ってたイメージと違うなみたいな、そういうところからなんか変わってくのかなあとか思ってたりはしてます。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 以下、ネタバレを含みます
植村 終盤の「あなたはきっと私に名前を付けるでしょう」という一連の台詞に気迫を感じました。これだけ匿名性をベースにした作品だと名付けに積極的な意義を与えるのが自然な道かと思うんですが、そうではなくて名付けが孤独に結びつくという……。
池田 そこはもう自分の思うところだなあというか。この物語のベースっていうか趣旨ですよね。
植村 名前についてどうお考えなんでしょう。
池田 個性を際立たせるっていうのがあると思うんです。世界に一つだけの花じゃないけど。僕はあんまりそうは思わなくて、みんなクローンだったらいいなあと思ったりする瞬間も結構あったりするんですよ。こんだけ人がたくさんいて、優劣も、異なってることもあって。異なってることがいい方向に働くこともあれば、悪いってことも相当あると思って。そうなった時に上下に縛られるっていうのじゃない別の次元に行きたいなって思って。個性とは別の場所ってなるともう自分は誰かわからなくなるし、自分ってものに名前も付けなくてもいいし。
植村 『ウエア』というタイトルはどのタイミングで思いつかれたのでしょう。
池田 一番最初に、舞台とか気にせず好きなものを書いてもらいたいって言われた時に、一番強く感じてたのは名前を付けるっていう。『ウエア』っていう名前も名前がぼやける名前にしたかった。母音だけの表現にして変化できそうな、色んな文字に変化できそうな、スタートとしての名前かなっていう感じで。一応皆さんはお金払って観に来てくれてて、じゃあ何に対してお金を払うっていう目印として『ウエア』っていう名前を付けたわけです。『ウエア』っていう名前から離れて名前を付けられるか付けられないか、っていうベースがあるって感じ。
植村 そのコンセプトで最初に作られた名前が「ニコンロ(※1)」と「ナミ(※2)」なわけですよね笑。
※1 『ウエア』の登場人物のひとり。
※2 『ウエア』の登場人物のひとり。
池田 なんででしょうね笑。僕にもさっぱりわからないです。何で出てきたのかなあ。名前もなんとなくそいつらがそういう名前を呼ばれてるんだなっていう次元からきてて、自然なイメージで。他の人にこう付けられたんだなっていう。で岡(※3)も最初に名前は正樹で「私は正じゃない方がいい」みたいなこと言ってるのも付けられた名前ってことで。ニコンロとかナミとかっていう人も誰かこういう経緯をもって名前を付けた人がいるっていう想像から生まれたっていう感じですかね。
※3 『ウエア』の登場人物のひとり。
植村 「メグハギ(※4)」という名前は自然に音の印象から選ばれましたか?
※4 『ウエア』の登場人物のひとり。
池田 最初は「恵まれる」とか「剥がれる」っていうそういう名前を考えてたんですけど、あまりしっくりこなくて、全然考えてなかったら勝手にふと「メグハギ」って名前がなんか浮かんできて。
植村 『ウエア(UEA)』というタイトルを意識すると「岡(OKA)」という名前は意味深な感じがします。そこに子音が混じることに意味はあるのでしょうか。
池田 たぶん『ウエア』っていう名前を付けてから「岡」っていう名前が出来てきたと思います。意味があると思います。正樹っていうのも岡的に本当は「止」っていう字が好きなのに上に一本加えられるっていうこととか、自分の好きなものになにか加えられるっていうことで、そこにフラストレーションが溜まって色んなことをやりだすみたいな人も多いなって思ってて。母音だけで成ってるものになにか加えられることによって変化が起きたっていう感じかなあ。
植村 池田さんは岡に自分を投射されていますか? それともどちらでもないのでしょうか。
池田 いや、どちらでもないと思います。誰にも感情移入してないです笑。誰にも感情移入は出来ないですね……。寧ろマジ何やってんだろっていうか。これあったらやだわあと思って書いてますね。
植村 岡が子音を剥ぐ話としては読めるわけですね。
池田 確かに。そう捉えられても全然いいですね。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 池田さんにとってこの感覚の方がリアルなのかなっていう感じはすごくあって。テキストが小説とかというよりかはWEBを読む経験に近いですよね。複数の情報が、重要度を比較できない状態で並列しているじゃないですか。PC的な知覚をだいぶ意識されているのかなあと。
池田 かなり意識して書いたと思います。
植村 僕は『動物化するポストモダン』を連想しました。
池田 笑。
植村 色々な情報が平面的に置かれているなというか、あらゆることが互いに交換可能な場所に置かれている感じがあります。
池田 たしかにある気がしますね。自分が今何を信じて何を信じてないのかって、ネットにもあるしいろんなところにもあるしみたいな。で、嘘をつく楽しさだったりついつい言っちゃう冗談の中に本音があるみたいな、いろんな人に共通してる部分があるんだなあとか思いながら作ってましたね。全部を信じるっていうことがそんなに僕はできないので、例えばこのコンセプトがあってこのために作りましたっていうのをどうしても信じられなかったりする。すべてのものを均等に見せる表現をしましたって言われてもピンと来なかったりする場合が自分にはあったりして。なんか作品作るにしてもコンセプトっていうのがどうも腑に落ちないまま……。そういった意味で、それをディスるわけじゃないけど笑。自分で書いたのも言ったのも嘘だな、ほんとにそんなこと思ってるのかなみたいなことをずーっと思いながら書いてたって感じでした。
植村 中澤さんがこの前の稽古の時に、原作中に出てくる宮沢賢治を太宰治と間違っていらっしゃいましたね。太宰は初期の『晩年』なんか嘘に嘘を塗り重ねる作風なので、僕はほんとに太宰の名前があったんじゃないかって気がして。
池田 そうですね、間違えてましたね笑。ああいうの別に僕大丈夫だな。僕も「太宰治あったっけなあ」って。それくらいふわっとしてたってのがある。
植村 池田さんはどんな作品がお好きなんですか?
池田 彫刻家の船越桂さんの作品が好きですかね。彫刻をやりたいなって思ったのは彼の作品を観てプラス墓石とか見て作ったんで。あと映画とかだと『スタンド・バイ・ミー』とかすごい好きですね。それも墓繋がりで見たような気がします。
植村 お墓がお好きなんですか?
池田 墓参りとか毎年行ってて。そこから色んな好きなイメージが湧いてくるので。死んじゃったものが彫刻物として見えるみたいな。お水は上からあげたりっていうのもある種の作品として見えたりするなっていう。船越桂さんの作品もそういうのがイメージとしてあったんです。
植村 たしかに船越さんの人体表現には不定形なものにむりやり形を与えているような不思議な所がありますね。
池田 なんかこう顔だけ残ってるみたいな、置物として存在してるみたいな、なにか生命的だけど同時に動いていない物的なものっていうのが、面白いなって思った。そう見ると色んなものも生物的にも見えるし逆の静物にも見えるっていうか、その境目がなくなるなっていう、そういう視点が生まれたなっていうのがありました。
植村 静物画って、死せる自然ということですもんね。
池田 そうですね。そういう色んなものがフラットに見える瞬間って面白いなっていう。
植村 それはゆうめいでの活動にも通底する発想としてありますか?
池田 あると思いますね。さっき『スタンド・バイ・ミー』って言ったんですけど、たぶん『スタンド・バイ・ミー』がゆうめいの方なのかなって。死体を探しに行くっていう物語に惹かれて。生と死の境目がわからないっていう状態でエモーショナルで物語性があってっていうところに行くところの表現は面白いなって。ゆうめいっていう存在はだいぶそこから引っ張って出来てきたんじゃないかなあと。
植村 全てがフラットになるというのは『ウエア』でもすごく顕著ですよね。特に生と死がフラットになる感覚については、『ウエア』ではどの程度強いんでしょう?
池田 『ウエア』では生と死はそんなに出てきてなくて。生と死のことをあまり描こうって感じにはならなかったですね。
植村 これだけ虚実の境が見えないつくりで死の匂いが希薄なのは不思議な気がします。
池田 それは自然にそうなっていましたね。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 これは勝手な推測かもしれませんが、ゆうめいの作風から離れた『ウエア』という作品に原作としてかかわる一方、なかばこれまでの総括的な『ゆうめいの座標軸』を発表されるわけですよね。それはゆうめいの活動に区切りがついた感覚があってのことでしょうか。
池田 確かに何となく、ポートフォリオじゃないですけど、ここまでやってきたことってのを見せてもらう企画でいいかなあって思ってたりしますね。ちょっとした区切りは確かについてるかもしれないですね、自分の中で。なんか新しい分岐点みたいなこともあるような気がしてますね。
植村 新しい分岐点。
池田 そうですね笑。でももともと『ウエア』は自分がずっと書いてきたものにすごい近くて、逆に言うとゆうめいがわりかし特殊な気がしますね。
植村 『ゆうめいの座標軸』についてコメントなどあれば。「座標軸」という言葉は随分示唆的ですよね。
池田 『弟兄』って作品があるんですけど、わりかし前作の『姿』に一番近いと思っていて、それはかなり実名を出したりとかして、現実がどうなったかっていうのを発表するっていうのに近い作品になってるんで、それが今のゆうめいのベースなのかなっていう。『俺』っていう作品は旗揚げの時にやったんですけど、一応現実から引っ張ってはいるけど、名前とかは全部創作だったり、創作の部分を加えたりとかして、もう終わっちゃった出来事とかあった出来事を経ての創作みたいな感じなんです。『弟兄』は現実でこういうことがありましたっていう発表なんですけど『俺』の場合はこういうことが現実にありました、それをもとに色々な目線で創作してみましたみたいな、その創作の中にはフィクションだったりが盛り込まれているっていう。一番旗揚げ公演がそういう感じだったんですね。旗揚げがだいぶ実話とフィクションが混ざってるっていう感じですかね。過去的な、過去に対しての創作物みたいな。
植村 『弟兄』の方は、過去の記憶を扱いながらも現在的な表現だったということですか?
池田 『弟兄』の方は現在形のものが入ってるなっていう感じですね。そうですね。
植村 それは今なお現在形のものですか?
池田 今なお現在形っていう感じが強いですね。だいぶリアルタイムを交えてる気がしますね。
植村 ゆうめいで作品を書くことの暴力性についてお聞きしたいです。書くことによって抑圧的な記憶に対しての復讐を果たしている側面があったのではないかと思うのですが、以前稽古で撮影された動画ではご自身の加害性について告白なさっていましたよね。それはこの復讐に一つケリがついたということなのかなと感じたんですが。
池田 だいぶケリはついてますね。『弟兄』もだいぶ自分の加害性にケリをつけた上での創作になるなっていうか。再演と言いつつ『弟兄』もちょっと変わってたりとか、自分の加害性とかいろんなものも盛ってったりとかしてだいぶ俯瞰して見るようになったなとは思いますね。
植村 それは『姿』という作品が大きいですか?
池田 だいぶ大きかったと思います。俯瞰する視線になっていますね。研ぎ澄まされたって言うのに近いのかなあと思います。『弟兄』の初演と再演はなんだかんだ言って自分の欲求みたいなのを結構ダイレクトに出してたなあとか思ってたりしてそれが暴力性に繋がってたんですけど、暴力性も顧みた上での再再演はそういった意味の自分をさらに俯瞰してるって意味での現在の発表みたいな感じになるなと思います。
植村 俯瞰というのは『ウエア』にも通じるところがありますよね。それだけ現在の心境がそちらによっているということでしょうか。
池田 元がそうだったのかなあと。匿名っていうものに対しても俯瞰できたからやってたんですけど、ゆうめいでいざ自分の名前を出すってことになった時に、実名を出すことへの視点がそこまで定まってなかったんじゃないかなあっていう部分があったりとかして、それが多分暴力的に見える場合もあるなっていうのは感じますね。暴力的に見えていいとは思うんですけど。
植村 距離を取って暴力をふるおうという?
池田 っていう感じなのか、でもやっぱりすごい不思議なことに、現実がそうはさせないというか。暴力をしている人に対して、なにか暴力は良くないっていうことだったりが実際起こったっていうものが、最近あったために、『弟兄』は結構暴力性が削がれているものになったなと。初演と再演は自分に暴力を振るってきた人に実名を出して糾弾するみたいなことやってたんですけど、その人から連絡が来ちゃって、で、「もう名前出さないでもらいたい」って、で、こっちも「名前出さないようにする」っていう。ある種暴力が暴力を押さえつけられたっていうことだと思うんですよ。向こうも暴力やってたけど、こっちも暴力したら、向こうもやめてもらいたいっていう、その。じゃあ一応抑えますけどっていう、そういうなんかあーやっぱ暴力性って出せば抑えてくる人はいるんだなっていうのがすごい強く感じて。
植村 一度実名を出されたことに対してはどう向き合ってゆかれるのでしょう。
池田 向こうは「公演では出さないで」って言ってるけど、でも別に個人で出しちゃダメとは言ってないから、公演が終わった後に気になる人は聞いてくださいっていうそういう感じですかね笑。電話してきた人たちも「これ以上」って言ってたから、今まで出しちゃったことに対してはもう容認してるのかなって自分の中では思ったから、じゃあこれから先はそういう関係の変化も現在進行形で表れるなっていうか。その関係の変化ってこっちが実名出すって暴力を削がれたものだし、向こう側から来たアプローチで関係が変わったって形になる。
植村 そういうことですと、これまでのバージョンをご覧になった方でも楽しみ甲斐はありそうですね。
池田 楽しみ甲斐はすごいあると思います笑。あーあいつだれだったっけなあみたいな。頭文字だけ言おうっていう演出を今してて。たとえば今から言うのも仮名なんですけど、「佐藤 洋平」さんみたいな人がいたら「さささ ささささ」みたいなそういう言い方をするみたいな。「さささ」役を演じる人も「あ、俺さささ、さささ。覚えてる?」みたいな。一種、初演再演を観た人にとっても「あれ、規制がかかってる」っていう面白さだったり。
植村 図らずしてゆうめいの方でも匿名性が増しているわけですね笑。
池田 そうですね、コンセプトとか全く別でやってたのに。こっちは現実を意識してて向こうはフィクションを意識してきたんですけど、図らずとして現実で現実的なことが起こったから匿名性に寄せられるみたいなことはありました。
植村 それはハプニング的なことではあるでしょうけれども、その匿名化になんらかの意味を感じたりはしますか。
池田 現実を意識してきたのにフィクション性が増すっていうのは面白いなっていうか。またそれが別の時空じゃないですけどこういうことが起きるんだっていうのは不思議に思いましたね。初めて再再演から観た人にとっては本当なのか嘘なのかわからなくなるんじゃないのかなっていうのは。
植村 今後ゆうめいで池田さんが発表される作品がどのようなスタイルのものになるのか見通しは立っていらっしゃいますか?
池田 一応なんとなく予想してるのが、たとえば『姿』ってやつは現実の諸事情によって、本当は現実を全部描きたいけど現実を全部描いたら問題が起きるっていうのが、それは法的なものとか、実際にその、被害を蒙る人とかも出てくるから、ところどころフィクションを入れてますってことだったんですけど、で、それで成り立ってたんですけど、次ゆうめいでやろうとしてるのは「全部フィクションですよ」って言いながら全部本当のことをやろうかなっていう風に考えてますね。
植村 その手つきは今ここで晒しちゃって大丈夫なんですか笑。
池田 たぶんまあ、そうですね。気付く人は気付くしみたいなことになるし。フィクションと言いつつ現実にかなりアプローチしたものになりそうだなと思ってますね。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 池田さんとスペースノットブランクのお二方との信頼関係は厚いなと感じます。お二方は他の方の舞台芸術作品についてあまり言及しない印象があるんですが、池田さんの作品についてはよく話していたので。
池田 そうですね。中澤さんに関しては以前二度ゆうめいに出てくれて、一番最初に出たやつはかなりフィクション性の高い舞台で今のゆうめいとはまた全然違う、それこそ自分のやりたいものとか、詳細とか緻密に作っていくものじゃないものを作ってたので、そこに出演してもらって、その次にいまのゆうめい的な、蓄積しながら実話の軸は変わらないものを作ってきて、その二作品、フィクション性の高いものと、ノンフィクション性の高いものに出てもらった時に「フィクション性が高いものの方がおもしろい。で、そっちの方を書くべきだ」とずっと言ってきてたから笑。僕一人が作るものっていうものにすごい興味を持ってくれたんだなあと思います。ノンフィクションだと取材してそこのつながりで作ってるってことだから、ベースがノンフィクションにあるから、それだと複数色んな人に関わって来るから、ってなるんですけど、僕一人だけのところからスタートして物語作ってた方がおもしろいって言ってたんで。
植村 フィクションから出発した方が池田さん的だと。
池田 そうですね。
植村 『ウエア』全体の中で何割くらいが池田さんの実体験から引き出されているんでしょうか。
池田 たぶん一割にも行ってないくらいだと思います。間に入って来るアニメとかのやつは自分の経験をもとにしてフォーマットを作ってますけど、自分の経験だったり、噂話からもってきたりすることとかあったり。自分の実家の近くに実際その、鳩小屋があって、そういう薬物とかやってる人がいてみたいなことは知ってるけど、そこは実際はそんなに踏み込んでないしみたいな。何かそういう場があったなっていう。実際本当にそういう場があったのかっていうのも自分に疑問を持っているところがあったりして。
植村 実際に「ヨクジョー浴場」があったことはお聞きしました。
池田 あー実際そういう場所はあったりは。名前は変わってたり、風俗ルポみたいなシーンも大分嘘とか盛ったりしてて。
植村 ゆうめいの場合は嘘を混ぜ込むことは少ないですか?
池田 結構少ないと思います。見せ方は変えてるけど芯の部分は変えてないなっていう。芯の部分をベースとして、変換して表現してるっていうのがゆうめいなんですけど、こっちの場合は芯の部分ごと変換してるから。
植村 形式にご自身の経験は生かされているけど、中身にはあまり使わないし、使っても嘘を入れるし、ということですね。その中で池田さんの記憶を用いた箇所には、特別な意味があったりしますか? お聞きしていて、あえて記憶の中でもあやふやなものから立ち上げているのかなという気がしました。
池田 そうですね。そこもありますね。あやふやで、あやふやだけどこっちが勝手に想像してイメージつけて肉付けてるみたいな部分とかあったり、あとは自分の体験から引っ張ってきてる部分とかって後々読み返せばわかるんですけど、その時書いてるときは全く別の時空で書いてるみたいなのがあったんで。
植村 書き終えて後でその意味に気付かれた箇所があるということですね?
池田 プール教室のシーンでジャグジー潜るっていうところあったじゃないですか。あそこ僕ジャグジー自体一回も潜ったことなくて。ジャグジー潜るの恐いんですよね。
植村 じゃあ「ヨクジョー浴場」のシーンも嘘なんですか?
池田 嘘ですね。一回も潜ったことないです。ジャグジーって僕トラウマがあって。月曜日のコナンとかが終わった後にやってた世界まる見え!何とか特捜部ってやつで、ふざけて温泉に潜っちゃった海外の女性が排水溝かなんかに引っかかっちゃって窒息しそうになってそれをレスキュー隊が救うみたいなVTRをちっちゃいときに見たんですね。そん時に怖えなって思って。ジャグジーとか水がぐーって出てるああいうところになんかの拍子に引っかかっちゃったら、髪の毛が引っかかったりして出れなくなったらどうしようって思ったりして、かつジャグジーだから泡ばっかりでどこにひっかかりがあるのかわからないっていう、それが凄い怖くて、ジャグジーは絶対潜らないって決めてたんですね。それを思い出しました。ジャグジーって絶対自分は潜らないって考えてたし潜ったら怖いってなるけど、勝手に潜った時の風景とか想像してできたから、それで後で読み返して、なんでジャグジーのシーン書いたんだろうなって、あーそこかーみたいな。自分の潜んなかった場所とかをすごい考えてたりしますね。
植村 ない記憶だけどトラウマに出発している。そこでも嘘と現実が混じり合っていますね。
池田 そういえばジャグジー嫌いだったなみたいな思い出されたりして。書いてるときは全然そんなこと思ってなかったんですけど、どっか想像で書いてる場所は自分で体験しえなかった場所を描いてたんだなあみたいな、そういうことは思いましたね。
植村 この前の稽古で話されていたカーペットのエピソードも印象深かったです。
池田 ああ、人形がどっか行っちゃう話。あれも多分あそこの場で話すのが初めてで、それ以外で話したことなかったんですよ。『ウエア』っていう作品を初めてやる時に勝手に自分の中でイメージで岡ってやつがメーリスに送るとかってなってるときに、なんかすっげー汚い部屋で、ゴミとかすっげー散らばってる中でゴミを勝手にいじくってゴミに書かれてる文字とかどういうゴミが落ちてるのかとか端からずっとチェックし始めるみたいなイメージがなんか勝手に浮かんだんですね。最終的にカーペットが残ってて、それでカーペットの裏をめくってくみたいなそういうシーンが最初に頭に浮かんだから。
植村 それはヴィジュアルから先にイメージされたんですか?
池田 かなりヴィジュアルからでしたね。自分じゃ絶対そんなことしないし、したくもないし。
植村 ジャグジーにしてもカーペットにしてもトラウマ的なもの……?
池田 そういう意味だと僕はカーペットとか好きじゃなくて。ゴミとかたまっちゃうし、フローリングのままでいいなと思ってて。うち猫飼ってるんですけど、カーペット毛だらけになっちゃって掃除も大変だから、あとルンバが動きやすいからカーペットとか敷いてないですけど、なんかそういえばそうだったなあみたいなのが後になって気づくことがたくさんありますね。やっぱ自分の記憶から引っ張られてるのかなとか。カーペットってイメージが先から自分の経験に根付いてるっていうのはあったなーと思ったりとか。勝手にそうリンク付けてるのかもしれないですけど、自分の中で。カーペットの下にそういえばいなくなっちゃったなみたいな。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 『ウエア』は岡という人間がメグハギを作った経緯を遡る仕方で書かれています。その時間の流れの意識はなぜこの作品の中心に据えられたのでしょう。
池田 これを書き始めた当時にやってたバーチャルYouTuberという仕事で見つけた発想からきてたりしてて。設定ではAIってなってて、自分一人でやってるってなってるけど、世間ではそう言ってるけど実際は中にはたくさんディレクターとか僕みたいな脚本家の人がたくさんいるんですよ50人くらい。で声優さんもいて、勝手にモーションキャプチャーとかもつけて、で、それで「AIですよー」とか言って、AIじゃないことは視聴者も勿論わかってるんですけど、でも「ポンコツAIだな」みたいな発言をするっていう。そこの仕組みは面白いなって思ってて。みんななんでこの構造を知ろうとしないんだろうなあみたいな。たぶん構造はわかっているけど、構造をあえて知ろうとせずに楽しむっていう。初音ミクと結婚するみたいなニュースが前にあったんですけど笑、そういう風に創作物とかありえないものを本物に思うって人の自由なんだなって。僕の場合メグハギっていう存在信じていいし、メグハギの裏側はどうなってるのかっていう方向もやりたいなって思った。AIが勝手に書いた物語になってもいいし、同時にただ岡とか須田(※5)っていう実際の人間によって書かれたやつになってもいいし。いろんな肯定が出来るように書いたって感じはありますね。
※5 『ウエア』の登場人物のひとり。
植村 メグハギのルーツをたどるという構造がそもそも必要だったということですね。
池田 中身が知りたいって人は勿論いると思って。最終的にメグハギがAIなの? みたいな。じゃあメグハギはメグハギとして単体として存在してるものなのかなみたいな。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 池田さんにとって自分が一番やりたいことをやる場所はどこになってゆくのでしょう。
池田 もともと最終的にこうなればいいなと思ってるのが、結構でかいアトリエを建てたいなみたいな、そういうことを考えてたりしてて。例えばアトリエと美術館が一緒になってるみたいな空間が建てられればいいなと思ってて。那須塩原に藤城清治美術館というところがあって、そこは藤城清治って人がひたすら今まで描いた作品を展示してるんですけど、彼は主に切り絵を作ってる方なんですけど、自然と一緒に混じりあってるみたいなそういう建物を造って、そういう場が池田亮美術館じゃないけど、池田亮じゃなくて他のいろんな作品が混じりあう場になればいいなと思ってるんですよね。藤城清治さんがまだご存命で90なん歳まで生きてるんですけど、リアルタイムで進んでる感じがあるので。基本美術館とかって完成品をもってくって感じなんですけど、完成品じゃないものを展示していいなあみたいなこととかを思ってて。アトリエと美術館と劇場ですかね、そういうのがミックスされた状態の場を作れたら面白そうだなと思っていて。そういう感じがある種目標ではあるのかなあ。自分が作るものが一つの色にとどまらないように意識はしていますね。
植村 藤城清治美術館、ネットに全然情報が出てないから行くの躊躇してました笑。
池田 一回足を運んでみないとちょっとわからないですけど、良くて。藤城清治の美術館、受付の人がすごい藤城清治ファンで、「回ろうと思えば一日じゃ回れないですよ」みたいなすごい熱弁してくれるんですよ。受付の人が一番ファンみたいな。僕も基本やっぱいろんな作品を見るのがすごい好きなんですね、どんなものでも結構好きで。作りたいっていうのと同時に、見たいっていうのが両方あって。鑑賞者にもなりたいし作る側にもなりたいっていうのがすごい強いので。藤城清治美術館行ったときに、自分も作って置けるし同時に見れもする場が欲しいなって思ったのが正直なところですね。
植村 『ウエア』に原作としてかかわるという行為もそれに近いかもしれませんね。
池田 そうですね、近いと思います。それこそスペースノットブランクは俳優から言葉を持ってきたりとか、どっかから影響を受けて作っていて。自分は原作ってなってるけど、原作ってよりか自分の場? みんなが何か出してくれる場を提供してるのかなあとか思いながら。皆さんが結構自由に出してくれるのを僕は観賞するみたいな、そういうありがたい場ではあるなあと笑。
植村 一貫して場を作りたいという欲望がおありですね。
池田 それは強いと思いますね。場を作りたいってのは僕の匿名性とかっていうのに繋がってきそうな気がしてて。
植村 お話をお聞きしていて、やはりこれまでのゆうめいの作風からは今後離れてゆく感じがあります。演劇って作家を中心に観る傾向があって、ゆうめいは特にそう感じられますので。
池田 そうだと思います。作演はだいぶ根強くあるなと思いますゆうめいは。
植村 『ウエア』では仮フライヤーやポスターに制作者の名前が50音順でフラットに置かれましたが、それは池田さんのお考えに響きあうところがありそうですね。
池田 ある気がしますね。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 信頼っていうことが一つのテーマとしてありますよね。冗談を通じた信頼。それは自分という存在が希薄になる場所を作りたいという欲求に対応するものとしてあるのかなという気がします。
池田 そうですね。既読無視するってのが信頼につながるってこともあると思ってて。二人の関係的に須田は別にメールとかチェックしてなくていいし、岡も向こうはチェックしてるかわかんないけどとりあえず須田なら送っていいみたいな状態になってるみたいな。そこはある種の信頼関係だなって思って。お互いの秘密は言わないみたいな。ただ多分須田が「岡からこんなメール送られてきました」って言って岡がそういう噂を聞きつけたら岡も須田のこと沢山言うと思うんですよ。送ってきたラインだったり、須田が今まで考えてきたこととか。お互い半ば冷戦みたいな状態になってるっていうか。二人の冷戦ってある種信頼関係でもあるんじゃないかなって気がしてて。そしたらこっちもこうするぞっていう。
植村 スペースノットブランクが並行して制作している『氷と冬』もまさに個人間の冷戦のような題材を舞台へ如何に立ち上げるかという作品なので、そのお話はお聞きして驚きました。
池田 凄いですね、そうだったんだ。たぶん近いんじゃないですかねえ。だいぶ面白いですね。同じ時間を生きてはいて、ただお互いのことを他の人にはばらさないようにしてる。親密な冷戦だと思います。本当に一人だけに向かって無茶苦茶わけのわからない表現を送っている、しかも壮大な時間をかけてよくわからない脚本とか新聞だったりそういうのを送ってるわけだから相当力は使ってるんだなっていうそこはある気がします。
植村 稽古で、二人のやり取りは中澤さんとのLINEに似ているかもしれないという話が上がっていましたね。
池田 改めて言われるとそこまで似ていない気もしますけどね笑。こっちの方が結構力加わってる方だなって思ったりはします。あでもこれも『ウエア』書いて送ってるから結局同様のパワーはあるのかなとか思ったりします。
植村 岡が独りでメーリスに送っては自分で消してっていう親密さから、須田を導入したことで岡と須田という二人の間の親密さになった。そのことの意味は大きいかもしれませんね。
池田 たしかにデカいと思いますね。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 苦労を経て今の形の『ウエア』を完成させたとお聞きしました。具体的にその変遷をお聞きしてみたいです。
池田 最初は自分がメーリスに送ってた文章を全部書き起こしてて、グーグルの曜日とか書いてたんですよ。全部コピー&ペーストをこの文章の中に起こしてたんですけど、実際メーリスが消えるみたいなシーンをメーリスの中で本当に僕消してたりとかしてたから笑。
植村 面白いですね笑。それは残ってないんですか?
池田 残さずに送って、「残ってないの?」って言われても「いや実際消しちゃったから、消すってシーン実際消しちゃったから残ってない」ってことに笑。
植村 あれ、消しちゃった事実って本文中には含まれていますか?
池田 ここ(完成稿)には含まれてないです。消しちゃった奴もここには一応残すようにしたんですけど、初稿は消すんだったらほんとに消してたので、グーグルのサーバーたどれば残ってるかもしれないですけど、そういう見せるものとしては残ってないっていうか。僕しか知らないみたいなそういう意味で作ってて。それもある種の完成形だと思ったんですよね。実際書いたものを飛ばしちゃってるし。メーリスを消しましたみたいなそういうコメントがあったりとかするっていう意味での、そこのメーリスにリアルタイムで見てた人の時間でしかわからないものを作ってた笑。
植村 パブリックとプライベート、個性と匿名性の関係性が本当に複雑ですね。誰にも見えなくなることが個人的な形としてあるし、けれど文章が匿名化していくことが親密な個性の発露としてもある……。他には、目立った変更点などはあったのでしょうか。
池田 最初にメーリスで書いてることによって物語として成立してたんですけど、実際消し終わった状態で、自分だけ物語体験した状態で、そのなれの果てみたいな状態を送ったから笑、たどり着いちゃったものをお送りしてるから、それは物語が共有できないなっていう話になって、だったらもう途中に物語を入れ込むようにしていったって感じでした。だから間のその関係性とかをなかば説明っぽい感じで、点線とかで入ってる途中の須田的なやつとか追加されてったり、消しちゃったメーリスとかも追加してったりしたんで。
植村 物語を共有する必要が強くあり、なれの果て状態からそれを復元するためのガイドとして作られたのが須田だったということですよね。一回なれの果てにしちゃった動機はなんだったんですか?
池田 自分が一番楽しいと思っちゃったせいだったんですよね。到達したなって思って自分は消しちゃったし、たぶん本当にガッと書いて、なれの果てになったのがたぶん五分の一くらいしか残ってなかったんですよ。それに至るまでに「先ほどのメーリスを消しました世界は消滅します」みたいな事を言って笑、「じきにこのメーリスも消えます」みたいなことを送っといて実際に消してるから、そこはもうほんとに自分だけしか楽しんでないみたいな状態だったと思うんですよ笑。
植村 池田さんが前にしきりに「他の人が読んで面白いのかわからない」というようなことをおっしゃっていまして、これだけ面白く書けても不安になるものなんだなあと僕なんかは感じたんですが、たしかにその作り方だと何もわからなくなるかもしれませんね笑。
池田 ほんとうになれの果てに辿り着いちゃった所のを提示しちゃってたから。最初の「好きなように書いてください!」っていうところに、自分なりに応えすぎてたし、ところどころ「これ消しちゃたぶん彼ら求めてるのと違うな」と思うけど、多分今までで一番自分優先しちゃったんで。
植村 それは、より物語性をという形でスペースノットブランク側からブレーキがかかったということですよね。
池田 初稿でなれの果て出した時にもうちょっとそこに至るまでの経緯があってこその物語だなってことをおっしゃられてたので、確かにそれもそうだなっていう、自分の中で完結しちゃってたものを提示しちゃってたからなあっていう。これはもう好きなように書いていいっていうものの、葛藤みたいなものは凄いあったような気がしますね。書いたものを消したいし、消すことによって成立するし、とか自分の中で思ってたから。
植村 それは本当に大きな変化ですね。
池田 はい。でも消しちゃったものから改めて物語を立ち上げていくっていう意味では、またそこから別のものに変化していったなっていうのはありますよね。復元にはなっていなかったかもしれない。追加しましたね。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 そういえばこれが舞台作品の原作として書かれたことに意味があると思っていまして。起点や終点をどこに置いてもよい作りが採用されていますよね。
池田 舞台になることを想定しなくていいって言われてて、で、じゃあ舞台じゃないものを考えていいんだって時に、最初に思いついたのがメーリスだったんでそこからいずれ舞台になるってことはあんまり想定せずに書いてたかもしれないです。そこの自由さがフレキシブルな感じで逆に行ったのかなあと思いますね。逆に舞台にしようってなると色んな意図とかが加わって逆に読んじゃった人が「ああこここういう意図か」って思っちゃうけどそういう意図とか全くなしにメーリスっていう媒体で自分のやりたいものを書いたんで。
植村 その意味でもWEB的かもしれませんね。WEBを巡る経験って始まりも終わりもないので。
池田 そうですね。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 いま池田さんにとって中心的な表現媒体は演劇だとお考えですか?
池田 いや、それだけじゃないような気がしますね。もともとそんな意識があまりなくて、媒体っていうものはあまり考えたことがなかったかもしれないです。舞台とかだと一応お客さんが増えたりするから、よりそこに繋がりやすいツールではあるなと思ってて、でもそれ以外もやりたいものに応じて媒体は変わってくるなあとは思ってますね。舞台が確かに結構いま主になってるとは思いますけど。
植村 作品中で複数のメディアの表現が出てきます。映画のポスター画像でしたり、アニメの脚本でしたりとか。その理由をお聞きしたいです。
池田 極端な話いうと、メールでやりとりしてるとどうしてもなんか入れたくなっちゃったっていうのがまず一つにあって笑、同時に……例えばライトノベルってあると思うんですけど、途中に絵が挟まってるみたいな。僕初めてライトノベル見たときに「ちゃっちいな」って思って。ほんとだったら文字しか描かれてないものに途中挿絵があるっていう感じが、なんで入ってんだよみたいな。いきなりイメージを促進するようなことしてきたなとか思ったりしてて。でもどの小説にも表紙ってあるんですよね。本来だったら文字だけで想像させるってものだけど、確かに今まで読んできたものって挿絵もあるし、文学といいつつ視覚的なデザインだったりがあるなあと思ったので、そのデザイン的なことも考えて入れてったかもしれないですね。途中のイメージの共有みたいなのを敢えてさせようみたいな。読んでる人にとってもちょっと暴力的かもしれないけどここは共有させておこうみたいなのが強かった気がします。
植村 「ちゃっちいな」って感覚についてもっとお聞きしたいです。
池田 携帯とかいじってると広告とか入ってくるじゃないですか、あれすごい面白いなあと思って。TikTokとかインスタとかでもどうしても入ってくる。実際僕もそういう仕事をしてて、ソーシャルメディアをどう売り込むかみたいな。Youtuberの作家をやってるんですけどそれも途中で広告を入れなくちゃいけない。広告を入れるっていう作為的な行動が自分もやってみたいな、文章の中でっていう。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 『ウエア』の原作をそのままの形で公表することは考えていらっしゃいますか?
池田 あー、出来たらいいなとは思ってますね。その文章はこういうデザインで作っちゃったから、もし縦書きで作られるならデザインを変えたりとかするのかなとか思いました。
植村 それはいいんですか?
池田 どうなんですかね、まあそうなったらそれに変えるように書けるなって。いくらでも完成する方法はあるなって。
植村 縦書きか横書きかでPC的な視覚かスマホ的な視覚かっていう大きな違いが出るじゃないですか。さしでがましくて恐縮ですが、そこは慎重に考えた方が良いのではないかなと思います。
池田 確かに笑、そうですね。書籍化ってしっくり自分もきてなくて。電子書籍でも読めるし、電子書籍の場合って本のフォーマットには則ってない変換された文字でもデータとして配布されてるから、そういう配布のされ方でいいんじゃないかなとか思ったりとかしてて。データ化される際と書籍化される際にはまた違うデザインになりそう。
植村 PCは複数のウィンドウを平面的に並列できますが、スマートフォンではそれがあまりできないじゃないですか。それって大きな違いですよね。僕はこの形はあまり崩してほしくない気持ちがあります。
池田 そうですね、崩したくないですね。また書籍用にすると物語自体変わっちゃうから。
植村 PC的な横書きを捨てると、また別の作品になるはずですよね。表現はPC的ですが、扱われる表現媒体はスマートフォンを連想させるものが多いのが不思議です。というよりは、なぜ現代にこれだけPC的なものが作られたのでしょう。
池田 メーリスもパソコンで書いて送ってて。パソコンで書いたやつをスマホでチェックした時もあったんですね。で、最初に送ったのも、スマホでメーリスを送る場合とパソコンでメーリスを送る場合で異なってたと思ってて。最初にベースにパソコン的なのがあったっていうのはだいぶそうですね。途中で過去に戻ったりする時に、僕が最初に文字とか書いたのがパソコンだったっていうのがあるかもしれないですけど、最初にWindows95のイメージで書いてたんです。実際僕送ってたのは普通にiMacのグーグルのやつなんですけど、最初これを打ってた時は初期のパソコンから送ってるイメージがあって。過去のパソコンから今の状態を送ってるみたいなのを成り立たせたかったなみたいな。このパソコンは縦書きにしかできないパソコンですみたいなことを終盤位にヤニクってところで通信して。縦書きって偏見かもしれないですけど若干前時代的な事だなあと思ってて。前時代的な過去にこだわりながら横書きのメグハギがあって。そういうイメージがありましたね。
植村 二重の意味でマルチメディア的な表現ですよね。アプリケーションのレベルとデバイスのレベルと。読む側はその分ついていくのが難しいかもしれません。
池田 物語を信じている人が読むとわけがわからないっていうものになるんじゃないかなあとは思いますね。ゆうめいだとわけがわからないっていう感覚で終わらせないようにはしてるんで逆だなあとは思います。
植村 たぶんスペースノットブランクはわかるようには加工してくれないでしょうしね笑。
池田 そうですね。だからまあそれもどのみちそうなるのかなあって風には思ってるから。ただまあそこはわかんない人は聞いてくださいっていう感じですね。解説もしますし自分が一番よくわかってるのでっていう感じで。そういうルーツになればいいなあと。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村 「メグハギを書く際に意識していること」って文章が作中に登場します。そこに感情移入しやすさを心がけると書いてあったと思うんですけど、その意図に反するかのように、読み手がメグハギや須田や岡に没入するのをどんどん拒んでいく構造をこの物語は持っているじゃないですか笑。没入しやすく書くという手つきをさらしながらその逆を行くんですが、読んでいる僕としては、意識は散らされながらも感情移入と違うレベルで没入して読む感覚はあって、それが奇妙で面白いというか。
池田 そこの書いた文章は自分の中で意識して書かなくちゃいけないなみたいなのもあったりしてて笑、そういう意味で自分で書いたってのと同時に、没入すると言いつつ、メグハギの世界ってどういうものなのかとか、どういう人が読んでるのかっていうのがわからないので、とりあえず視聴者っていうか観る人にとって観る人が主人公みたいなことを書いたと思うんですけど、そういう意味でのリンクなのかなと思います。目の前でわけわかんないこと起こってるけど、一応読んでるのあなたですよみたいな。そこの目線は僕と読んでる人とある種共通してる部分かなあと思います。僕もわかんない世界を描いてるし、向こうもわからない笑。たぶんちょっとわかってるシーンとかある、わかってはいるんですけど、ただ、どうしてこの世界でこれはこうなるのかっていうのは自分でもわからない部分が結構あったりとかしてて、それが気まぐれなのかと言われればあんま気まぐれじゃなかったりとかいう感じがあったりとかして。
植村 僕はゲームの感覚なのかなって。たとえば『LIVE A LIVE』って主人公コロコロ変わるけど没入しないわけじゃないですよね。プレイヤーは常に自分だから視点は保たれていてみたいな。
池田 だいぶゲームの感覚、そうですね。アプリゲームの開発者の言葉からいろいろインスパイアされてたんで、そこのルーツから引っ張ってこられてる。ゲーム的な感覚にすごい近い。
植村 架空のキャラクターであるメグハギについての語りですけど、ゲーム的な感覚もかなり含まれているわけですね。
池田 そうですね。
植村 「主人公(とヒロイン)を明確にする」って、爆笑ポイントですよね笑。
池田 そうそう笑、全然明確にはなってないですもんね。そういう意味でもメールを送ってる人なりのギャグなのかなとか思ってたりはしてて。こんなこと書きながら逆のこと言ってんじゃねえかよっていうツッコミ待ちの状態みたいな、そういう遊びみたいな感じになってるんじゃないかなって。
植村 この前の稽古でマルチメディア的な表現の理由をお聞きしたときに、それぞれの表現によって、自分が今いる世界を確認しているというお話がありましたが、それは先ほどの「自分でも何を書いているかわからない」ってところに対応してくる気がします。
池田 書いてるといろんな場所に行くなあと思っていて。時折その場所を定めたりしてるのが画像だったりしてるんですけど。写実的な表現だったりすると、軸があって明細に描いていくことで物語が蓄積してくって感じなんですけど、時折僕はそこからワープしたくなる。ゆうめいとかいろんな人が関わっているとなるとそれはワープせずに行くと思うんですよね。細かいところから蓄積した物語を作りたいってなるのは、いろんな人が関わっててそれを丁寧にしたい、積んでいきたいみたいなイメージがあって。分散されるものは自分一人だったらできるなって感じがしてて。ただ自分一人で書いてるといろんなところに自分は行きたくなっちゃうんですよね。自分一人しかいないからどうしてもその、ワープしたくなるっていうか。
植村 そのとっちらかりはどの程度ご自身で計算されてるんですか?
池田 家帰ってユーチューブとかツイッターとかいろんなところチェックしようっていうその行動原理があると思うんですよね。帰ってきて、スマートフォン見て今までチェックしてたニュースだったりツイッターだったりユーチューブだったりを情報を得る為に動こうって思うみたいな、そこら辺を起点にしながら書いてたりしてるところがあって。じゃあなんで情報を仕入れたいのかっていうとなにか自分が発したいとか何か得たいって欲求だと思うんですよ。何かを学びたい何かを知りたいっていうその欲求って何だろうっていうことを考えながらいろんな場所にワープしてくっていうか。だからここにいても得られるものが無かったりもうちょっと知りたいものがあるなっていうんで、ワープさせようみたいな、場所を変えようみたいなのがあって。欲求の話が序盤とかに結構あったと思うんですけど。
植村 欲求の話は伺いたく思っていました。なぜ作中では、社会的な欲望でなく、一貫して動物的な欲求が描かれるのでしょう? そういう意味では個人的なものに出発して書かれているのでしょうか?
池田 知りたいって思う欲求だったり、何かを追求したい、どこに行きたいみたいなそこをわりかし主軸においてるような気がしてて。自分が書いてる上で、じゃあこれ書いてどうなりたいのかっていうのが、自分の場合はどんどんどんどん違う世界に行くけど、同時に今生きてるところも開拓していきたいみたいな、両方。現実もだし、外の想像の世界も開拓していきたいみたいな。その欲求って何なんだろうなと思うと、知りたいもそうだけどなんでこんな求めてるんだろうなみたいな、そこの根源的なものが凄い気になってきたっていうのがベースにあるような気がしますね。
植村 欲求にフォーカスするというのは池田さんの他の作風からは外れていますか?
池田 たぶん突出してるような気がしますね。ゆうめいとかだと自分の名前出して自分が作演で。他の人の目線とかもかなり気にしてて、池田がこういうことをやってるってことに対して誰かが欲求を満たしてくれるようなものを作りたいっていうのはあって。なのでゆうめいでやるのは表現っていうんじゃなくて発表っていう意識がすごいあって。今までこういうことがあって、こうなってこうなりましたっていうことを発表することによって他の人の欲求を引き出すみたいな。
植村 対して、『ウエア』ではご自身の欲求が強く出されている?
池田 そうですね。自分の欲求とプラス皆が感じてる欲求っていうのをたぶん結構同列に考えて作ってるなっていうのを思ったりしてます。他の人も気になるし、でも僕も気になってることがありますよっていう。でも他の人が気になってることは別に『ウエア』の中に入ってないけど、同じようなベクトルとか同じような欲求を書いてるっていう意味ですごい同じところにいると思うんですよね。他の人はこれは気になってるけど、でも僕もこれ気になってるっていう。そういう広いところの中で書いたっていう感覚は凄いあります。
植村 個人名を出しながら同時に匿名的な書き方がやはり採用されているわけですね。
池田 そうですね。匿名的になりましたねなんか。
植村 最初に書き出されたのはニコンロとナミのシーン?
池田 あ、そうですね。一番最初に思いついてたのはそこでしたね。
植村 その時点で『ウエア』全体の構想は念頭に置かれていましたか?
池田 最初は何となくあったっちゃあった。最初の構成として、そのニコンロとナミって奴とそこに通ってた奴って三人の関係性が頭の中にあったんですけど、そこの関係性が、自分が物語にした際に何かまた別の物語にある存在だなって思って。物語の中の物語みたいな。のがあって、じゃあ何の物語がベースになってるのかっていうのはメーリスだなっていうのはなんとなくイメージがあった。根っこの部分としてはそうでしたね。ドラッグだったりそういうのをやるのが、なんかそういう次元に飛ばされるんじゃないかなみたいな。
植村 じゃあワープ的なものを書きたいという意識から出発してドラッグのエピソードを選ばれたんですかね。
池田 そうですね。
植村 自律訓練法は実際なさってたんですか?
池田 実際やってましたね、実際やってました。実際やってたけどうまくいく人とうまくいかない人がいて、僕全くうまくいかなかったので。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
植村朔也 うえむら・さくや
大学生。1998年12月22日生まれ。小劇場と市街の接続をスローガンに批評とプレイを実践する〈東京はるかに〉を主宰。広くやさしく舞台芸術を批評し、日本の小劇場シーンの風通しをよくしていく。
東京はるかに
東京はるかに|批評
インタビュー
池田亮
額田大志
出演者インタビュー
荒木知佳と櫻井麻樹
瀧腰教寛と深澤しほ
イントロダクション
植村朔也
メッセージ
小野彩加と中澤陽
ウエア|作品概要