舞台の外で考える|番外編「照明について」──Dance Base Yokohama「Wings」セミナー:久松夕香「欧州と日本の比較から探る、舞台創作の関わりかた」レポート
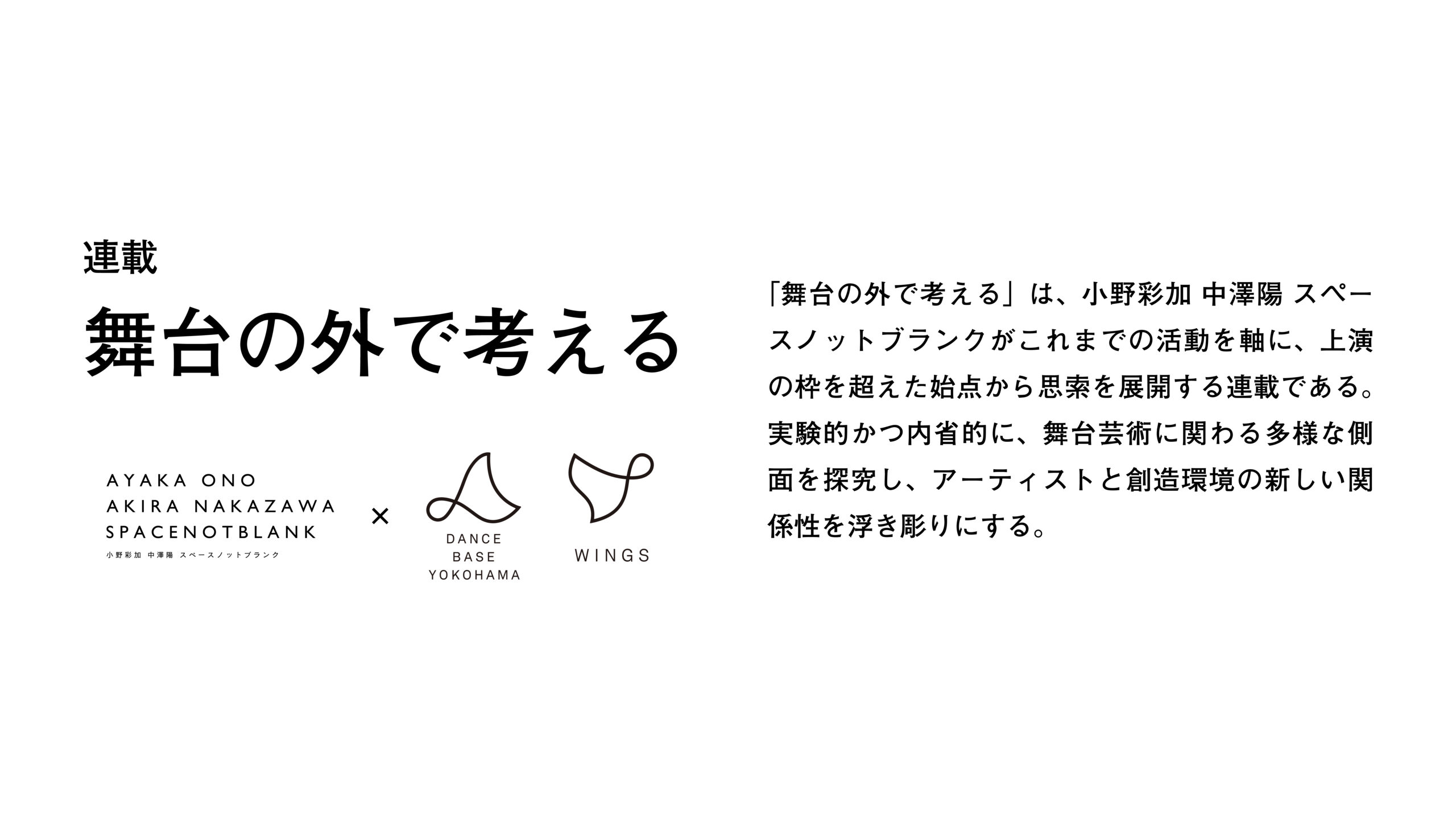 |
レポートは何故書かれるのか?
私たちは、舞台芸術の特定の領域を問わない二人組の舞台作家として活動してきた。活動の現場では、しばしば「わかりやすさ」を担保するための分類を求められるが、私たちにとってそれはどうでもいいことである。「わかりやすさ」とはつまり「そのもの」を否定する行為から開始する。「これはきっと何かである」という結果が求められるのだ。私たちはそれを嫌うからどうでもいいとしているのではない。「これはきっと何かである」という状態はすでにあらかじめ存在しているにもかかわらず、それをスルーして分類を開始すること、に重きを置いていないのである。「そのもの」が「そのもの」であるということから思考を開始したい。単に無知ということも当然あるが、既存のジャンル分類や制作過程の「当たり前」を一度取り外し、私たちの「仕組み(メカニズム)」を探し直すところから、クリエーションは開始する。身振りを取り扱う場合も、コミュニケーションを取り扱う場合も、まず最初に疑うのは「これは本当にこのようにしてあるべきものなのか」という「問い」である。
Dance Base Yokohama(以下、DaBYとする)による「世界に羽ばたく次世代クリエイターのための Dance Base Yokohama 国際ダンスプロジェクト “Wings”(以下、Wingsとする)」は、文化庁が創設した「文化芸術活動基盤強化基金」における「クリエイター・アーティスト等育成事業」の一環として位置付けられている。この事業は、若手アーティストや制作者を3年程度継続して支援し、創作から国内外での発表までを一貫して伴走する仕組みを掲げている。支援対象は舞台芸術に限らず広範に文化芸術領域におよび、「新たな芸術の創造」「文化施設の機能強化」「コンテンツ産業の国際競争力向上」などを目的としている。らしい。「Wings」への参加は、私たちにとって一種のフィールドワークのような意義を持ち始めている。ここで得られる情報や人脈、条件をどう活用するかは、あくまで私たち自身の戦略によって変化する。だからこそ、このレポートを書くことは、与えられた場としての「Wings」に対して一方的な「感想」を提出する行為ではなく、私たちから「Wings」を批評的に観察し、活用し、再定義するための行為としたい。
本レポートは、2025年6月27日(金)19:00より約1時間45分行なわれたオンライン形式のセミナーとその質疑応答のアーカイブ映像に基づくものである。このセミナーはオープンセッションとして「Wings」関係者以外にも公開された。私たちは「Wings」クリエイターとして特別に後日アーカイブ映像を視聴し、その内容と私たちの制作活動との関係を踏まえて執筆を開始する。
「文化芸術活動基盤強化基金」における「クリエイター・アーティスト等育成事業」に表される「育成」という言葉。舞台芸術に限らず文化芸術の世界では軽く使われがちな一方で、背後には歴史的な重みがある。戦後日本の文化政策では「人材育成」という語が繰り返し出現したが、その多くは、既存の枠組みや技術体系に若手を適応させるための制度であり、新たな構造や価値観を育てるものではなかった。対してヨーロッパのいくつかの制度においては「Artist Development」という言葉を使用し、既存のフォーマットを破壊して新たなフォーマットを創造すること自体を支援する場があるように見える。はたして「Wings」における「育成」はどちらに分類されるのだろうか。それを判断してしまう前に、私たち自身の戦略によって「Wings」の「そのもの」としての価値を考えたい。
今回のセミナーは、ヨーロッパで活動する照明デザイナーの久松夕香さんを招き、ヨーロッパと日本の制作環境の比較を軸に進められた。内容を雑にまとめると、「舞台創作の関わり」がヨーロッパは「早期関与型」で、日本は「後期関与型」である、という二項対立的な整理ができる。しかし私たちはそれだけを受け取りたいとは思わない。先の「問い」と連なるものとして、その話題が、DaBYと、そして「Wings」において、どのような位置付けを持つのか。それが気になる。このセミナーは理想像をシェアし、その理想像の不可能さに打ち拉がれるためだけのものなのか。あるいは実際に私たちの「育成」のためにやらせたいこととしての布石であるのか。後者の兆しは「まだ」見えていない。私たちが求めるのは、ただ「学び」を得て報告することではない。このセミナーを通して私たちが得た知見とこれからの機会を活用して、何に成るのか、何処へ進むのかを考えたい。そのために、舞台芸術の「照明について」に限らない、「照明」をありとあらゆる芸術領域に関係する要素として広く捉えながら、「学び」を私たちの「仕組み(メカニズム)」に取り込んでいく。
このレポートを書くにあたり、私たちは「なぜ今、照明について語る必要があるのか」という根本的な「問い」を立てる。私たちが求めるのはレポートを過程とした「創造」への接続。そのためにレポートという形式を活用する。私たちにとっての「Wings」自体の意味、価値を問い直す。そこで得た「考え」を未来の活動のための資源とする。それは、能動的な態度として、「育成」される側であるだけでなく、「育成」の構造そのものを設計し直す側に回ろうとする意志でもある。そして、私たちはこのレポートを、2025年3月にDaBYとともに実施した連載「舞台の外で考える」の番外編に位置付けることで、私たちがこの言葉を「誰に向けて書いているのか」を明瞭にすることにした。私たちを「育成」するのは、本質的に私たち自身、そして、貴重な人生の時間を割いてこの文章を読んでいる「あなた」に他ならない。
批評的距離を保つことは、時に歓迎されない行為でもある。現場では時間も資金も限られているため、批評以上に即応性や順応性が重視されるからだ。しかし、批評的な視点を欠いた現場では、無意識の内に既存の制度や価値観を再生産する危険性がある。だからこそ、「そのもの」の価値をどう受け止め、どう翻訳し直すかが重要になる。特に今回のセミナーでは、「現場ごとの柔軟性」や「早期関与の重要性」といった内容が強調されていた。だが、現実には私たちが全てのメンバーと初期から関わっている事例は少なく、むしろ後半になってから関わることが常態化している。もしもDaBYがリアルに早期関与型の制作モデルを普及させたいのであれば、制度設計や予算配分から変えていく必要がある。現場だけに柔軟性を求めても、その柔軟性を支える構造がなければ形骸化してしまうのは明らかだ。私たちが思考したいのは、「日本とヨーロッパ」という大きな主語の比較ではなく、日本国内の特定の制度やコミュニティに対して、「Wings」が何をもたらし得るのか、という具体的な影響についてである。グローバルな比較は魅力的ではあるが、それは往々にして抽象的でもある。現場に落とし込むには如何せん距離が遠すぎる。まずは私たちが立つこの場所、この制度、このネットワークにおいて、クリエーションをともにするメンバーたちとの「関わりかた」をどう変化させることが可能かを考えたい。
以上の視点を共有した上で、私たちは「照明」という言葉を、舞台芸術の文脈から一度引き剥がしてみたい。「照明」は、視覚芸術における構図を定めるだけでなく、物理的な空間の温度や湿度、さらには人間の生理的および心理的反応にまで影響を与えることができる。多角的な視点を持ち込むことで、「照明について」めぐる思考はどこまでも拡張する。私たちがこのレポートを通じて目指すのは、「照明について」を舞台芸術という領域のみに閉じず、「光」が社会や文化とどう関わり、どう変革を促し得るのかを探究することである。そしてその探究の過程で、DaBYの「Wings」を単なる研修と体験の場ではなく、実験と批評の場へと変えていくこと。それこそが、私たちが「Wings」に参加し、このセミナーを視聴し、レポートを書く最大の理由である。
セミナーでは何が語られたのか?
セミナーのタイトルは「欧州と日本の比較から探る、舞台創作の関わりかた」。久松夕香さんが「こんにちは、あ、こんばんは、か。」と、挨拶をする。「ヨーロッパで舞台照明のデザイン業務」そして「照明のチーフ業務」をしている久松夕香さんが、「欧州と日本の比較から探る、舞台創作の関わりかた」について、スライドを用いて知見を共有する場である。「私も正解を知ってるかっていったら、そういう話でもないんですけれど、皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思ってます。」と、前提が伝えられる。
スライドを再生し始める前に、日本で見られる「舞台の作り方」の光景についての一例が照明デザイナーの観点から示される。「作品がある程度出来上がって、通し稽古になって初めて照明デザイナーがやってきて、じゃあ通し稽古見せてくださいって言って、振付家だったり先生なんかが、ここは暗転が欲しいんです、ここはサスいただけますか。って。あー分かりました分かりました。じゃあ、それらしい明かりを作っていきましょうね。っていうような作り方をよく見かけることがあると思うんです。」続く別の例として「もう舞台に入って、舞台稽古になって、振付家の方だったり、お芝居だったら演出家の方がほとんど明かりづくりを進行してしまうようなパターンっていうのもあると思うんです。じゃあ、ここのシーン、じゃあ、SS、上手からのSS、50%頂戴。はい、これ次のキューで。じゃあ変化は5秒ぐらいにしてください。って言って、照明さんがあたかもその演出家、振付家のオペレーターのような。分かりました、じゃあこの明かりですね、じゃあ次のキュー5秒で入れますね。って言って、というような明かり作りをする光景。」という説明が為される。
その他にも様々に「舞台の作り方がある」が、先の2つの例を含む様々な「舞台の作り方」を分類してみたところ、「2つの軸」に「分けれるように考えてる」という。スライドが切り替わる。中央に縦書きで「作品の独創性」と記された画面。文字の左隣には、両端に矢印付きの青い縦線分が引かれている。「その軸の1つが、ここに書いてあるように、作品の独創性。どのぐらいオリジナルな作品なのか。それとも定番寄りの作品なのか。」という言葉に重ねて、画面上の上向きの矢印の上に「独創的」、下向きの矢印の下に「定番」の文字が浮かび上がる。「もう1つの軸っていうのが、それに関わるクリエイターへの依存度なんですけれど。」と言いながら、「作品の独創性」の青い縦線分に対して十字に重なる両端に矢印付きの赤い横線分と、「クリエイターへの依存度」の文字が出現する。そして右向きの矢印の右に「おまかせ」、左向きの矢印の左に「リクエスト」の文字が加えられる。「舞台の作り方」の「マトリクス」が完成した。
「小劇場」は「独創的」寄りの若干「リクエスト」寄り。2.5次元演劇などの「商業公演」は「定番」かつ「おまかせ」寄り。「発表会」は「定番」かつ「リクエスト」寄り。伝統芸能は「定番」寄りの若干「おまかせ」寄りに位置している。そして、先に述べられた「通し稽古で初見」する「舞台の作り方」は、「定番」かつ「おまかせ」寄り、「じゃあはい、OK、組みましょう、って言って見るのは、この右下の枠だと思ってるんです。でも、ある程度形の分かってる、全くびっくりするようなことがないからこそ、通し稽古まで待って参加、で皆さん問題がなくて、稽古を見てもらって、じゃあそれなりにそのようなそれらしい明かりを作りましょう。っていうような形ですね。」対して「振付家が全部デザイン」する「舞台の作り方」は、左上に位置している。「こういうやり方もね、全然悪くない。その作品のパターンによってはそれが一番都合が良かったりもするんですけれど、この関係って、振付家側がこういうものをやりたいです。こういう問題を解決したいです。っていうのを一方的に定義する側で、それを受ける照明家なりクリエイターが、そういう問題を抱えているのなら、じゃあこういう風に解決しましょう。じゃあそこの変化を5秒でしたいのなら、じゃあ5秒でタイムを組みましょう。とか、じゃあここで暗転が欲しいんだったら、じゃあそこで暗転が入れれるように設計しましょう。っていうような、どっちかって言ったら、ちょっとコミュニケーションが一方通行になりがちな形だと思ってるんです。」すなわち、左上に近付くほど「独創性は高いが振付家および演出家主導の指示型」になり、右下に近付くほど「定番的内容でデザイナーおまかせの効率型」になっていく。左下は「定番的内容で指示型の発表会など」。では、右上はどうなのだろうか。
「創造性、ある程度クリエイティビティがある作品。それに加えてその関わるクリエイター、デザイナーにも、おまかせできるだけの技量と、おまかせできる信頼関係とっていうのがあって初めて成立するのがここの右上の枠。」であり、「私は普段できる限り、ここの右上に辿り着けるようなクリエーションを目指しています。」という言葉が続いた。
久松夕香さんは2005年に照明を始め、クラシックバレエの照明専門の会社、様々な舞台の照明を行なう会社を経て2017年に独立。独立後、作品を深く理解せずとも「それらしいそれっぽい仕事」ができてしまう現実に衝撃を受け、「それらしい明かりを出すだけで仕事になってしまう」ことに疑問を抱き始める。その後、親しい振付家や演出家のプロジェクトに自主的に稽古初期から参加するようになる。さらにヨーロッパでは日本よりもデザイナーが創作段階から長く関わる環境が多いことを知り、2021年に文化庁の「新進芸術家海外研修制度」を利用して現在の就職先であるネザーランド・ダンス・シアター(以下、NDTとする)にて1年間の研修を行なう。研修後、NDTの照明チーフ兼デザイナーとして就職する。
というような内容の自己紹介が行なわれたのち、久松夕香さんの現在の役割の説明へと移行する。日本では「照明」が図面作成、機材手配、キュー整理、仕込みおよびフォーカス、本番のオペレーションまで幅広く担い、舞台監督や制作も多くの業務を兼任している。一方ヨーロッパでは、「プロダクションマネージャー」が存在し、照明、大道具、音響など舞台全体の技術面や予算、スケジュール管理を一括して行なう。場合によっては「キューマスター」が全てのキューをまとめる役割も担う。そのため、ヨーロッパの「照明チーフ」の業務は日本より範囲が狭く、本番に関わる実務中心となる。また、「照明デザイナー」などを擁する「クリエイティブチーム」と、舞台監督や「照明チーフ」などを擁する「テクニカルチーム」は明確に分かれ、「照明デザイナー」は「テクニカルチーム」ではなく「クリエイティブチーム」の一員として位置付けられている。この構造が、日本との大きな違いである。
こうした構造的な違いを踏まえた上で、NDTでの制作プロセスが紹介されていく。NDTでは大規模作品の場合、1年前から1年半前に制作が始まる。30分程度の中規模の作品でも、およそ8ヶ月前には本格的な準備が動き始める。最初の段階では振付家との顔合わせが行なわれ、作品の構想の有無にかかわらず、振付家の背景や創作の原動力、興味の対象を知ることが重視される。過去作品や関連する文学、映像作品を相互に提示し合い、共通のイメージや言語を形成していくのである。この時点で「照明デザイナー」は単なる「スタッフ」ではなく、作品世界をともに構築する創作者としての立場を明確にしていると言える。稽古前には予算と機材の調整を兼ねた仮の照明プランが提出されるが、ムービングライトを多用することで後の変更にも対応できるようにする。稽古が始まると、可能な限り初期から現場に通い、振付や動きが生成される過程を観察し、その意図を共有する。稽古場で浮かんだ明かりのアイデアはスケッチとして蓄積し、振付家との対話によって修正および発展させる。コミュニケーションは一方通行ではなく、双方の発見を促すための反復作業となる。舞台稽古は本番の2、3週間前から始まり、トリプルビルの場合は1作品に割ける時間が数日に限られる。それでも長期間の準備によって、この段階は「試作」ではなく「完成に収束させる場」として機能する。ヨーロッパでは初日が完成の到達点とされ、その後クリエイティブチームが現場を離れる場合も多く、日本のように千穐楽まで精度を高め続けるような文化とは異なる。
作品が初日を迎えた後の展開には主に3つのパターンがある。1つ目はツアー公演。NDTでは初日後1、2ヶ月で数十回の上演を行ない、繰り返しによって参加者の解像度が上がり、作品が真に完成していく。上演数の多さは作品の命を太くする重要な要素である。2つ目はフェスティバル参加。ガラ・コンサートやコンペティション形式では特別な照明セットが組めないことも多いが、それを前提にシンプルに作るべきでは決してない。むしろ初演時は、再現不可能でもいいほど作り込み、後から核心部分を抽出する方が有効で、その翻訳には信頼できる「照明デザイナー」が不可欠である。3つ目は再演。NDTでは1、2年後の再演時に振付家やデザイナーが戻らず、リハーサルディレクターや「照明チーフ」が資料を基に復元することが多い。再演を前提に作る意識は、余計な要素を削ぎ落とし、作品を長く生かすポジティブな作用を持っている。
久松夕香さんは、振付家と照明デザイナーなどのクリエイターとの関係は、舞台に上がるずっと前から始まるのが理想であり、信頼関係があれば振付家が全てのデザインを抱え込む必要がなくなると述べた。長期的な協働を重ねることで、双方は作品の文脈やテーマをより深く共有できるが、必ずしも同じチームで作り続けることだけが正解ではなく、テーマやコンセプトによってメンバーを変えることも有効だとする。初めての顔合わせでも、十分な時間をかけた事前のコミュニケーションが、誤解や時間不足による突貫的な対応を防ぐと強調した。また、日本とヨーロッパの「舞台の作り方」の違いを紹介しつつ、どちらが優れているという単純な比較ではなく、双方の「いいとこ取り」をする姿勢が重要だと述べた。海外に作品を持ち込む際は、現地のやり方に単に合わせるのではなく、独自の方法論や文化的背景の「違い」を強みとして活かすことが肝要であり、その「違い」を恐れず作品や対応に反映して欲しいと締め括った。
私たちは何をしているのか?
私たちは今、「照明」という言葉をどのような意味で切り取り、取り扱っているだろうか。「照明」は単なる「光源」に非ず、本来「照明」とは人間の感覚、知覚、文化、環境と深く結び付いた「現象」であると考えていきたい。今回のセミナーを契機に、これまで以上に「照明」を「舞台芸術の技術的手段」としてではなく、「体験を構築するための普遍的なメディア」として捉え直し、私たちの「舞台の作り方」すなわち「仕組み(メカニズム)」に組み込む必然性を強く感じている。
映画における照明を考えてみる。舞台とは異なる制約と自由を持つ映像の現場では、カメラが捉える光の感度や色域に合わせたライティングが求められる。照明は映像ジャンルの美学や物語構造に直接的に作用し続けてきた。ゲームではどうだろう。リアルタイムレンダリング技術の進化によって、プレイヤーの行動や時間帯に応じた動的な光の表現が可能になった。光はインタラクティブな体験の感情設計と直結している。これは舞台における照明の在り方とも似ている部分がある。美術館での展示やインスタレーションでは、作品の保存性と鑑賞性を両立するための照明設計が求められる。紫外線や熱を避けつつ質感や色彩を忠実に伝達するための、緻密な光の操作が行なわれる。照明は「見せる」ためでなく、「守る」ためにも機能する。舞台における光も、観客の感覚に働きかける「表現」のためのみならず、出演者や空間そのものの安全性を確保するという役割を担っている。拡張していくとどこにでも「照明」が存在していることがわかる。都市や環境デザインにおいて、光は防犯や交通安全といった実用面に加え、都市のアイデンティティや観光資源としての価値を持つ。光の色や強度が、街の雰囲気や人々の活動のリズムすら変容させる。この視点を舞台に取り込み、あらゆるサイトスペシフィックを「そのもの」として舞台化できるかもしれない。
照明の歴史は、技術革新の連続であると同時に、人間社会の変化と密接に関わり続けている。古代の松明やオイルランプは宗教儀式や権力の象徴として存在し、中世ヨーロッパの大聖堂ではステンドグラスが自然光を演出し、信仰心を高めた。近代にはガス灯や電灯が人間の夜間活動を拡張し、都市生活を変えた。照明は常に文化的および社会的な変革の触媒だったのである。この文脈を踏まえると、舞台芸術における「照明」を単なる要素の一つまたは補助的要素として捉えるのは大きな誤りであることが明確にわかる。「照明」を起点とする作品の設計が、これからの時代においてより作品の固有性を強化することに繋がっていくだろう。
こうして思考を続けていると、「照明」はあらゆる領域、時代を超えて、人間の体験をデザインし続けてきた共通の要素であることを実感させられる。今回のセミナーで得た最大の教訓は、「照明」を専門領域や特定の役割に閉じ込めず、「違い」を前提とする異分野や異業種の知見をクリエーションに統合する姿勢そのものが創作の戦略になり得るということである。私たちはDaBYの「Wings」を、単なる知識習得の場としてではなく、こうした異分野的な「照明観」を実際の創作に組み込むための試験場と位置付けたい。セミナーで紹介されたマトリクスの「右上」のクリエーションを目指すには、何をすればいいのかを考える。私たち自ら「関与」の在り方を設計し、新しいモデルを提示していく。その第一歩として、『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』を創作している。
私たちは何をしていたのか?
今回のレポートを通して改めて確認したのは、「照明デザイナー」の立場から論じられた「舞台の作り方」および「舞台創作の関わりかた」は、直接的に私たち自身の創作姿勢と深く関わっているという事実である。例えば、久松夕香さんによって示された「(上演する場所によって特別なセットが組めないことがあるが、それを)前提にシンプルに作るべきでは決してない。むしろ初演時は、再現不可能でもいいほど作り込み、後から核心部分を抽出する方が有効」という指摘があるが、『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』は、国内外での発表を目指し「ツアー前提でなるべくコンパクトに作る」ことを当初より意識しており、その前提をチーム全体で共有して受容できているものの、それは久松夕香さんの指摘とは対照的な意識であることがわかる。その上で私たちは何を取捨選択すべきなのか、が問われている。今回のセミナーで得たヨーロッパと日本の比較の知見は、その「問い」を考えるための入口でしかない。重要なのは、知見をどのように私たちの制作戦略へと翻訳し、現実のプロジェクトに組み込むかという点である。与えられた条件に適応するだけでなく、枠組みそのものの「仕組み(メカニズム)」を作る姿勢で創作を続けていく。ヨーロッパにおける「早期関与型」のモデルもあくまでひとつの参考例として捉え、私たちの創作を通して日本の現場や制度に則した新たな実践という形で応用および定着させられるかを考えたい。その意味で、今回のセミナーは知識を得る場であると同時に、次の実践へと踏み出すための「問い」を獲得する機会だった。
「照明」を始点とする議論は単なる技術論ではない。制度、経済、文化、身体感覚と密接に結び付いた総合的な問題であり、そのいずれも切り離して考えることはできない。このセミナーを通じて私たちの創作環境を批評し、再設計する必要がある。「Wings」が目指す具体的な制度としての価値は「まだ」見えていないが、その状態は自主的な設計と提案の余地があることを意味している。「育成」を受動的に享受するのではなく、能動的に介入し、私たちの成長と現場の構造改革を同時に実現することこそ、本来の「Artist Development」ではないだろうか。『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』で、どこまでその姿勢を具体化できるかはわからない。作品世界の理解を深めた「照明デザイン」。観客の体験全体を視野に入れた「上演デザイン」、そして制作過程そのものを再構築する試みを複合的に捉え、私たちの創作領域を拡張するための実験に臨みたい。
今回の久松夕香さんによるセミナーは、「舞台の作り方」における人と人との「関わりかた」に焦点を当てていたが、その「関わりかた」を経て完成される実際の「表現」がどのようなものになるのか、非常に興味深く、好奇心が湧いている。今後の機会があれば、そのような点についても知見を伺いたい。そして舞台芸術に限らず異分野における照明の価値についても、独自に知見を広げていきたい。本レポートは、その出発点である。全ては「次」の一手であり、私たちは、私たちの「次」に期待し、選択し、実行していく。
2025年8月21日(木)
小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク
助成:文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業)|独立行政法人日本芸術文化振興会

これまでの「舞台の外で考える」
第1回「演出補について」
第2回「滞在制作について」|Dance Base Yokohama
第3回「喪失について」
第4回「企画について」|Dance Base Yokohama